■派遣先メーカーにも賠償命令/労災死亡事故訴訟、東京地裁
派遣社員だった長男が勤務先で死亡したのは会社が安全対策を怠ったためだとして、両親が人材派遣会社(神奈川県)と派遣先の容器メーカー(東京都)などを相手に計1億
9,200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が 13日、東京地裁であった。裁判長は直接の雇用関係がない派遣先の責任も認め、2社に計約 5,100万円の支払いを命じた
裁判長は、Aさんが勤務中に意識を失い、作業台から落ちて死亡したと認定。テクノ社について「転落防止の措置を取らなかった」と責任を認めた。
派遣先については、同社の機械・設備が設置された場所で作業が行われ、管理もしていたと指摘。「派遣社員との間には、実質的に使用者と労働者の関係が生じており、安全配慮義務を負う」と述べた
判決によると、 2003年8月、大和製罐東京工場で缶のふたを検査していた際、高さ 90センチの作業台から転落して頭部を強打。約3カ月後に死亡した。(時事通信)
■男女別賃金は違法 東京高裁 女性4人逆転勝訴
総合商社(東京)の社員と元社員の女性6人が、「男女別の賃金制度は不当な差別」として、同社に差額分賃金や慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決が31日、東京高裁であった。
西田美昭裁判長は女性側の請求を退けた1審東京地裁判決を変更。男女の賃金格差が違法だったことを認め、4人に対し計約7250万円の支払いを命じた。
主な争点は、男女の賃金を分けた制度は違法かどうかだった。総合商社(東京)は「職務内容が違うコース別賃金制度で、男女差別ではない」と主張していた。
西田裁判長は、4人の賃金は、同じような困難度の仕事をしていた男性社員と比較して相当の差があったことを認めた。その上で、「この差に合理的な理由はなく、性の違いによって生じたと考えられる」と判断。男女の差によって賃金を差別していた兼松の違法性を認定した。
1審判決は、平成11年に改正法が施行される前の男女雇用機会均等法下では、男女の差別的扱いをしないことは雇用者の努力義務だったと指摘。男女を分けた処遇は違法ではないとしていた。(産経新聞)
■「店長は管理職に当たらない」…残業代の支払命じる・東京地裁
日本マクドナルドが店長を管理職扱いにして残業代を認めないのは違法として、埼玉県内の直営店店長が未払いの残業代と慰謝料などを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であり、裁判官は「店長は管理職に当たらない」として計約750万円の支払いを命じた。
訴状によると、1999年10月に店長に昇格。管理職に相当する「管理監督者」として扱われ、残業代などが支払われなくなった。
店長になった後も、(1)店頭で直接接客している(2)出退勤時間の自由がない(3)アルバイトの採用権限はあるが、人件費を厳しく制限されているため、自由に採用できない−などと主張。管理監督者には当たらないと訴えた。
月100時間以上の残業をした時もあったのに、残業代がないため、月給が部下を下回ることもあり、管理監督者として処遇されていないと指摘。時効にかからない約2年間の未払い分計約517万円などを求めた。 (時事通信)
■「勤務の質が過重」/看護師の過労死認定、大阪地裁
看護師の長女がくも膜下出血で死亡したのは過重な勤務が原因として、大阪府吹田市の夫婦が国を相手に、国家公務員災害補償法に基づく計約 1,260万円の遺族補償を求めた訴訟の判決が 16日、大阪地裁であった。
裁判長は「勤務と死亡の因果関係は、超過勤務時間の面からは認められないが、質的過重性を考慮すると認められる」と述べ、ほぼ全額の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決によると、長女=当時(25)=は国立循環器病センター(吹田市)の脳神経外科病棟に勤務。2001年2月に自宅でくも膜下出血を発症し、翌月死亡した。
発症前6カ月間の時間外労働は毎月約 50時間で、裁判長は「時間的(量的)な過重性では、発症は公務に起因するとは言えない」と指摘。しかし、1カ月に5回程度、勤務終了から次の勤務まで5時間程度しかない体制が組まれていたことから、「精神的、身体的負荷は非常に大きく、慢性疲労や過度のストレスが持続、蓄積していた」と認定した。
同じ看護師の母親は記者会見で、「看護の現場の労働条件は本当に厳しい。これを機に改善につなげてほしい」と話した。(時事通信)
■個人業務委託のエンジニア、労組法上の労働者と判断/INAXメンテナンス事件
会社と個人業務委託契約を締結して修理業務などに従事するCE(カスタマーエンジニア)が加入する組合からの団体交渉の申入れに対し、INAXメンテナンス(常滑市)が「CEは個人事業主であり労組法上の労働者に当たらない」と応じなかったのは不当労働行為だとして、救済申立てがあっ事件で、中央労働委員会は10月31日、命令書を交付した。「CEは、会社の基本的かつ具体的な指図によって仕事をし、そのために提供した役務にき対価が支払われている」とし、CEを労組法上の労働者と判断した初審命令を維持。申し立ての全般を不当労働行為に当たるとして救済を命じた。
■住み込み管理人にも残業代/「時間外も住民対応で待機」、最高裁
夫婦でマンションの住み込み管理人をしていた女性(67)が雇用主で大林組子会社の「大林ファシリティーズ」を相手に、残業代など約 4,000万円の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は
19日、「所定労働時間外にも、住民らに対応できるよう待機せざるを得ない状態に置かれていた」と述べ、残業代は支払われると判断した。
その上で、通院や犬の散歩に使った時間は「管理人の業務とは関係ない私的行為」とし、実際の残業時間算定のため、審理を二審東京高裁に差し戻した。
同小法廷は、夫婦は平日午前 9時 〜 午後
6時の所定時間以外にごみ置き場の扉の開閉や、空調設備の運転切り替えなどの仕事をしていたとして、平日の労働時間を午前 7時〜午後 10時と認定。
2人分の残業代が支払われるべきだとした。
管理マニュアルで、管理人室の照明が点灯している間は時間外でも宅配便などに対応すべきだとされていたとし、「残業は会社による黙示の指示だった」とも指摘した。
判決によると、夫婦は 1997年から 2000年まで、東京都北区の 13階建てマンションを住み込みで管理していた。(時事通信)
■NTTの年金減額認めず/「経営状況悪くない」、東京地裁
退職者への企業年金減額を厚生労働省が認めなかったのを不服として、NTTグループ
67社が国に処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は
19日、「減額がやむを得ないほど、経営状況が悪化していたとは認められない」として、NTT側の請求を棄却した。
裁判長は「NTT東日本と西日本は、厚労省による不承認処分の前の決算で、1,000億円前後の当期利益を上げていた」と指摘。「(将来)大幅に減益となり、掛け金を拠出することが困難になると予測させる証拠もない」と述べた。
NTT側は減収減益の傾向が続いており、年金減額はやむを得ないと主張していた。
判決によると、NTTグループは 2005年 9月、企業年金を減額するため、「確定給付企業年金法」に基づき規約変更承認を厚労省に求めた。しかし、同省は昨年
2月、要件を満たしていないとして、不承認とした。(時事通信)
■パワハラ自殺、労災と認定/上司暴言でうつ病、東京地裁
製薬会社の男性社員=当時(35)=がうつ病にかかり自殺したのは上司の暴言が原因として、男性の妻が国に労災認定を求めた訴訟の判決で、東京地裁は
15日、「上司の言動で過重な心理的負荷を受け、精神疾患を発症させた」として労災と認め、遺族補償給付を支給しなかった静岡労働基準監督署長の処分を取り消した。
原告側の弁護士によると、パワーハラスメント(職権を背景とした嫌がらせ)による自殺を労災と認めた判決は初めてという。
裁判長は「上司の言葉は男性のキャリアだけでなく、人格や存在自体を否定する内容もあった」と指摘。上司が男性の立場などに配慮せず、大声で叱責(しっせき)したと述べ、「通常の上司とのトラブルを大きく超える心理的負荷があった」として、暴言とうつ病発症との因果関係を認めた。
国側は上司の発言について、男性に対する指導、助言だったと反論したが、「指導的な意図があったとしても、(男性の)心理的負荷が軽減されるか、はなはだ疑問だ」と退けた。
判決によると、男性は 1997年 4月から同社静岡営業所にMR(医療情報担当者)として勤務。上司の係長は 2002年
4月に同営業所に赴任し、男性に「存在が目障りだ。消えてくれ」「給料泥棒」などと暴言を繰り返した。男性はうつ病を発症し、03年 3月に自殺した。
■入社半年で自殺、労災と認定/「過重業務で心理的負荷」、福岡地裁
長崎県内のソフトウエア開発販売会社に入社し、約半年後にうつ病などで自殺したシステムエンジニアの男性=当時(
24)=の遺族が、国を相手に労災認定を求めた訴訟の判決で、福岡地裁は
27日、業務と自殺の因果関係を認め、福岡中央労働基準監督署の遺族補償一時金などの不支給処分の取り消しを命じた。
裁判長は、男性について、納期に迫られながらシステムのトラブル処理などで、「過重の心理的負荷があった」と認定。男性は半年の間に勤務時間が急増し、自殺直前の出張中は、徹夜で作業を続けていたとした。
国側はシステムのトラブル処理はさほど困難でなかったとしたが、裁判長は「初めての処理で、応用力も必要とされた」として退けた。
判決によると、男性は 2000年 4月入社し、福岡支店でシステムエンジニアとして勤務。同年 9月
26日、千葉県に出張中、遺書を残してホテルで自殺した。(時事通信)
■出版社バイト掛け持ちで自殺、26歳女性に労災認定
出版社2社で掛け持ちアルバイトをしていた東京都杉並区の女性(当時26歳)が自殺したことについて、東京労働者災害補償保険審査官が労災を認定した。
東京過労死弁護団事務局長の尾林芳匡弁護士と女性の母親(55)が16日、明らかにした。
女性は杉並区のコミック誌の出版社に社員として勤めていたが、2004年9月に新宿区の別の出版社にアルバイトとして採用された。このため杉並区の出版社では正社員でなくなり、10月は両社をアルバイトとして掛け持ちしたが、精神疾患となり、同29日に静岡県内の実家で自殺した。
両親は「精神疾患による自殺は業務上の災害だ」として労災保険給付を申請したが、新宿労働基準監督署は06年1月に「業務と精神疾患に因果関係はない」と判断した。しかし、東京労働者災害補償保険審査官は、両社合わせた時間外労働が月147時間に及び、自殺前日に杉並区の出版社社長から兼業を約4時間もしっ責されたことを重視し、労災認定した。 (読売新聞)
■「ばかやろう」で解雇は無効/ブラジル人通訳勝訴、名古屋地裁
仕事で上司とやりとりした際、「ばかやろう」と言ったことを理由に解雇されたのは不当として、日系ブラジル人の男性通訳(35)が、勤務先の人材派遣会社(静岡県浜松市)を相手に、地位確認などを求めた訴訟の判決が9日、名古屋地裁であった。
裁判官は「発言は 1回限りで、合理的な解雇理由とはいえない」として、昨年 7月の解雇処分は無効と指摘。会社側に解雇時から判決確定まで月当たり 35万
5,000円の給与を支払うよう命じた。
判決によると、原告は、派遣先の自動車部品会社で、通訳や一緒に派遣された日系ブラジル人らの勤務管理を担当。昨年 5月、上司と有給休暇の申請方法をめぐり、電話で口論となり「ばかやろう。おれは子どもではない」と発言したところ、翌月解雇された。 (時事通信)
■過労自殺、二審も労災認定/遺族補償不支給取り消し、福岡高裁
子会社に出向していた単身赴任の男性=当時(48)=が自殺したのは過労によるうつ病が原因として、兵庫県内に住む妻が福岡県内の労働基準監督署長を相手取り、遺族補償年金不支給処分の取り消しを求めた控訴審判決が7日、福岡高裁であった。裁判長は「自殺は業務に起因する」として、処分を取り消した一審福岡地裁判決を支持、労基署側の控訴を棄却した。
原告側によると、高裁段階で過労自殺が労災認定されたのは、トヨタ自動車の係長だった男性=同(35)=のケースで名古屋高裁が
2003年に認めて以来 2件目。
訴訟では、労災の判断基準が争点となり、労基署側は自殺の原因は本人の「脆弱性にあった」と主張。しかし、同裁判長は平均的労働者と比べて「性格等に過剰な要因があったと認めることはできない」と指摘した。
判決によると、男性は 1999年 8月、福岡県筑後市の子会社に出向した後、精神障害を発症。同年
12月に同社倉庫内で首つり自殺した。
同労基署は 01年 9月、労災認定せず遺族補償年金などを支給しないことを決めた。(時事通信)
■過労死で賠償命令/「受動的対応では不足」
共同通信によると、仕事中に倒れ急性心筋梗塞(こうそく)で死亡した北海道旭川市の男性=当時(55)=の遺族が、月平均 180時間に及ぶ時間外労働をするなど過労が原因として、生鮮食品加工業(北海道旭川市)に約
6,660万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁は 23日、約 3,380万円の支払いを命じた。
裁判長は判決理由で「会社は労働時間を短縮するための措置を何ら取らなかった」と指摘。「事業主は、労働者からの長時間労働の申告を受けて対応すればいいという受動的なものではない」として、積極的に過労死対策を取る義務があるとの見解を示した。
判決によると、男性は 1998年からは管理部長として経理などを担当していたが、 04年
2月、仕事中に意識を失い、急性心筋梗塞で死亡した。死亡直前の 3カ月間の休みは 2日だけで、月平均約 180時間の時間外労働をしていた。
■外勤社員の出向認めず/「不利益変更」と東京地裁
共同通信によると、損保最大手の東京海上日動火災保険(東京)がセールス担当の外勤社員制度を廃止した上、代理店へ出向させようとしているのは労働条件の不利益変更で無効として、外勤社員
46人が正社員としての地位確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁は 26日、全員の請求を認めた。
裁判長は制度廃止や配転に経営政策上の必要性があることを認めた上で、会社側は外勤社員を採用した際、転勤のない営業専門職として「職種限定契約」を結んだと指摘。「会社側が提示した配転の条件では大幅な減収になり、転勤がないという保障もなく、原告は大きな不利益を受ける」と判断した。
判決によると、同社は
2004年、東京海上火災保険と日動海上保険が合併して発足。外勤社員は旧日動が採用し、歩合給制に近く顧客との関係を維持するため、転勤もなかった。
合併当時は外勤社員制度を維持することで合意していたが、05年 10月に制度を今年
7月までに廃止するとして退職を募るとともに、継続雇用希望者は代理店へ出向させる方針を提示した。出向の場合、給与水準は従来より 9〜
17%程度減額され。転勤もある。
原告側によると、会社側の提示前に約 920人いた外勤社員のうち、約 850人が退職し、現在は 68人しか残っていないという。
■「社内飲み会も業務」 帰宅途中に死亡で労災 東京地裁が認定
社内で開かれた会社の同僚との飲み会に出席して帰宅途中に地下鉄駅の階段で転落して死亡したのは労災に当たるとして、妻が中央労働基準監督署を相手に、遺族給付など不支給処分の決定取り消しを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。裁判長は労災と認め、決定の取り消しを命じた。
裁判長は会合について「業務を円滑に進める目的で開かれており、業務上の成果も出ている飲酒は忌憚(きたん)のない意見交換をするため」と認定、会合が業務だったと判断した。中央労基署は「会合は勤務時間外に開かれた慰労目的で業務でなく、労災に当たらない」と主張していた。
判決によると、死亡したのは東京都内の建設会社の部次長だった男性。男性は平成11年12月、勤務時間外の午後5時から社内で開かれていた会合に出席し、缶ビール3本などを飲んだ。約5時間後に帰宅する途中、地下鉄駅の階段から転落して頭を打ち死亡した。
(産経新聞)
■新入社員は過労自殺/労災不認定取り消す
共同通信によると、栃木県の食品卸会社に入社し、約 8カ月後に自殺した男性=当時(23)=の両親が労災と認めなかった真岡労働基準監督署(栃木県)の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は
27日、過労による自殺と認め、処分を取り消した。
判決によると、男性は大学卒業後の 2002年 4月に入社。同社宇都宮支社の営業担当に配属され、10月から 2社の取引先を任された。
時間外労働は 9月まで月 50時間未満だったのに、10月からは月 150〜 112時間に急増した上、取引先とのトラブルや売り上げのノルマを達成できない悩みも重なった。
12月中旬までにうつ病を発症し、同月 24日、自殺した。
真岡労働基準監督署は 04年 8月、自殺は業務が原因ではないとして労災と認めず、遺族補償を給付しない処分をした。
両親が長時間労働を放置し、安全配慮を怠ったとして、同社に 1億 2,000万円の損害賠償を求めた訴訟は今年 7月、会社側が約 2,000万円を支払うことなどを条件に東京地裁で和解している。
■自動車メーカー社員の過労自殺認定/約6千万円の支払い命令
共同通信によると、自動車メーカーの)に勤めていたAさん=当時(41)=が2002年に自殺したのは過酷な業務やストレスが原因として、同市の両親が自動車メーカーに約9,100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、静岡地裁浜松支部は10月30日、過労による自殺を認め、同社に約5,867万円の支払いを命じた。
裁判長は「月平均で約 100時間もの時間外労働をさせ、上司がうつ病の発症をうかがわせる事実を認識しながら何ら措置を取らなかった」と指摘、安全配慮義務の違反を認めた。
判決によると、Aさんは 1983年に入社し、座席シート部門に勤務。 02年 2月に四輪車体設計部門の責任者(通称課長)に就任後、仕事の重圧や長時間労働などからうつ病を発症し、同年
4月、会社の屋上から飛び降り自殺した。
■アクセス記録で過労証明 死亡男性の労災認定
共同通信によると、電車内で倒れ死亡した東京都内の男性=当時(42)=について、八王子労働基準監督署がパソコンの接続記録を基に長時間労働を認め、労災認定していたことが
21日分かった。遺族の代理人の弁護士が明らかにした。
弁護士によると、男性は大手事務機器メーカーの課長だった昨年 6月、東京都千代田区から八王子市内の事業所に向かう途中、JR中央線の電車内で倒れ、
5日後に虚血性心疾患で死亡した。
男性の労働時間を証明する資料を会社側が示さなかったため、遺族側は東京地裁八王子支部に労働時間についての証拠保全を申請。これが認められ、男性がパソコンで同社のコンピューターサーバーにアクセスした時間やメールの送信時間、文書ファイルの更新時間などが判明したという。
この結果、男性の死亡前 3カ月間の平均時間外労働が 1カ月当たり 86時間だったことが証明され、労災と認められた。
■7年後処分は権利乱用、社員2人の懲戒解雇無効/最高裁
共同通信によると、上司への暴行などを理由に食品メーカーを懲戒解雇された2人が、社員として地位確認などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷は6日、告敗訴の二審東京高裁判決を破棄、解雇を無効として同社に未払い賃金の支払いを命じた。同社敗訴が確定した。
■残業1時間で死亡も労災/作業条件厳しく逆転勝訴
共同通信によると、船舶の荷物積み降ろし作業後に心臓病で死亡した港湾労働者の男性=当時(48)=の遺族が、大阪西労働基準監督署長に遺族補償給付などの不支給処分取り消しを求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁は
28 日、作業条件の厳しさなどから労災と認め、遺族の逆転勝訴とする判決を言い渡した。
男性は心臓に持病があったものの、死亡前 1 週間の残業時間は 1 時間程度で、原告側弁護士は「従来の基準では認められなかったケース。労災を幅広く認めた判決だ」と評価している。
裁判長は判決理由で、不整脈など男性の持病について「心臓病発症寸前までは悪化していなかった」とした上で、死亡までの勤務状況を検討。
1 週間の残業時間が約 1 時間で、直前の 2 日間が休日だったため「負担が重いと断定するのはためらう」としたが、死亡時が夏で直射日光を浴びて作業していたことから「前の週に比べ厳しい業務となった」と判断。業務により心臓病が発症したと認定し、不支給処分を取り消した。
判決によると、男性は 1995 年 7 月、大阪市住之江区で早朝から貨物船に鋼材を積み込む作業をしていたが、午後八時ごろ倒れているのが見つかり間もなく死亡した。作業現場に日よけはなく、最高気温は 30 度を超えていた。
■三重銀が8億7千万不払い/2年間の残業代を精算へ
共同通信によると、三重銀行(三重県四日市市)は 15 日、 2004 年 2 月から 06 年 2 月までの間、行員約 1,200 人に対し、計約 8 億 7,000 万円の時間外手当の不払いがあったと発表した。近く全額を精算するとしている。
四日市労働基準監督署は今年 2 月、三重銀に対し、行員の時間外労働の実態を調査するように勧告していた。
こ れを受けて三重銀は、 04 年 2 月から今年 2 月までに在籍した支払い対象行員約 1,450 人を対象に、パソコンの使用履歴や金庫の開閉記録などを基にした実態調査を実施。このうち約
1,200人への不払いが判明した。
不払い金の平均は一人あたり約 70 万円。最高額は 30 代後半の総合職の男性で、約 550 万円という。三重銀は労基署の指導を受けるまで、行員の自己申告だけを基に時間外手当を支給しており「適正な申請さえあればきちんと支払っていた」と釈明している。
現職行員に対しては今月 28 日に全額を支給、退職者についても来月以降支給する予定。
同行の加藤幹博専務は「法令順守の観点から誠に遺憾。労働時間の厳正化を行いたい」としている。
■退職後過労自殺も労災/不認定取り消し国敗訴、「業務で発病、治らず」
共同通信によると、過重な労働でうつ状態となり無認可保育所を退職後に自殺した保育士の父が死亡を労災と認めなかった国の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は4日、請求を認め、処分を取り消した。
難波孝一裁判長は「業務によって発病し、うつ状態が治らずに自殺したと認められる。自殺の原因が業務ではないとした労働基準監督署の処分は違法」と判断した。
退職後の過労自殺で労災が認められたケースについて、厚生労働省労働基準局補償課は「把握している限りない」と話している。
判決によると保育士は 1992 年9月に保母(現在は保育士)の資格を取得。翌 93 年1月から無認可保育所に勤務し、月曜から土曜まで 12
時間勤務が続いた。
3月末には、同僚の保育士6人全員が退職し、4月から責任者として新人5人を指導することになった。3月 31 日に病院で適応障害と診断され、入院のため退職。翌日退院したが、うつ状態が続き、4月 29 日に自宅で自殺した。
父親は同 12 月、労働基準監督署に労災申請したが、同労基署は「退職、退院で障害は治っていた」として認めなかった。労働保険審査会への再審査請求も昨年3月に棄却され、同6月に提訴した。
夫妻は保育所の経営会社に損害賠償請求訴訟も起こし、 98 年8月の大阪高裁判決は業務と自殺との因果関係を認め、経営会社に約 570 万円の支払いを命令。
2000 年に最高裁で確定している。
■「左遷でうつ病」労災認定/1人だけ窓際、給料11万減
共同通信によると、化粧品製造会社の元社員の男性が「左遷人事が理由でうつ病になった」とした労災申請について、労働基準監督署が労災認定していたことが
30 日分かった。
申請を支援した弁護士は「精神疾患の労災認定は過労が原因であることがほとんど。こうしたケースでの認定は非常に珍しく画期的だ」としている。
男性は 1996 年に同社に入社し本社経理部で係長を務めていたが、2004 年7月に突然、群馬工場の総務部に転勤になった。男性側は「同僚だった社長の息子に嫌われたことによる左遷人事だろう」としている。
職場ではほかの社員の机とは離れた場所で、窓に向かった席に着かされた。給料も月約 11 万円減った。男性は転勤の2カ月後にうつ病になり、3週間入院。退院後の同年
10 月に本社に出向くと、解雇を告げられたという。
男性は 05 年4月に労災申請し、同年5月には解雇の無効と損害賠償の支払いを会社に求める訴訟を起こしている。
男性は「認められてよかった。今回の認定が、同じような状況で苦しんでいる人たちの一助になれば」と話している。
■7500万円支払いで和解/生命保険会社所長の過労死訴訟
共同通信によると、生命保険会社の営業所長=当時(32)=が死亡したのは過労が原因として、妻らが会社に損害賠償などを求めた訴訟は22日、会社が和解金など7,500万円を支払うことなどを条件に大阪地裁で和解が成立した。
■2,000万円支払い和解/月100時間残業の新人自殺
共同通信によると、栃木県の加工食品卸会社に入社約8カ月後に自殺した男性=当時(23)=の両親が、月100時間を超える時間外労働を放置し安全配慮を怠ったとして、勤務先に1億2,000万円の損害賠償を求めた訴訟は7月31日、会社側が約2,000万円を支払うことなどを条件に東京地裁で和解が成立した。
■過労自殺、遺族と和解/コマツ、裁量労働下で初
共同通信によると、仕事の性質上、勤務時間などが労働者に委ねられる裁量労働制の職場で働き、過労自殺したAさん=当時(34)の遺族が長時間勤務を放置したなどとして、勤務先の機械メーカー「コマツ」(東京)に計約1億8,000万円の損害賠償を求めた訴訟は7月28日までに、東京地裁で和解が成立した。
■元従業員ら勝訴確定/仙台のタクシー会社訴訟
共同通信によると、労使合意に反して年末一時金を支給しなかったのは不当として、タクシー会社の元従業員ら63人が同社に一時金の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷は18日、同社の上告を退ける決定をした。同社に計約2,000万円の支払いを命じた二審仙台高裁判決が確定した。
■社員の過労自殺認定/納期迫り、残業159時間
共同通信によると、2002年に男性=当時(28)=が自殺したのは、過労が原因だとして遺族が出した労災申請について、いったん申請を棄却した厚木労働基準監督署が、あらためて労災と認定したことが12日、分かった。監督署は当初、自殺する直前1カ月の残業時間を会社の説明を踏まえ117時間とみなしていたが、再調査で159時間に上っていた実態が判明したことなどから認定を見直した。
■成果給与に変更合理的/減額3社員が逆転敗訴、東京高裁が初判断
共同通信によると、給与制度が実質年功序列型から成果主義型に変更され、降格・減給した企業の社員が減給分支払いなどを求めた訴訟の控訴審判決が、東京高裁であった。裁判長は「制度変更には高度な必要性があり、内容に合理性がある」として原告勝訴の一審横浜地裁川崎支部判決を取り消し、請求を棄却した。
■均等法の相談件数、3年連続で増加/労働局雇用均等室
厚生労働省は5月29日、2005年度の均等法施行状況をまとめた。全国の労働局雇用均等室に寄せられた均等法に関する相談は1万9,724件と3年連続で増加。セクシュアルハラスメントに関する相談が4割を占めている。
■過労による脳・心臓疾患の労災認定、330件に増加/05年度、厚労省
厚生労働省は5月31日、2005年度に過労で脳・心臓疾患にかかった人などの労災認定状況をまとめた。請求件数は869件で前年度に比べ53件増加。
認定件数は330件で前年度より36件(12.2%)増え、このうち過労死の労災認定は157件だった。また、働きすぎなどによる精神障害の労災申請は656件で、127件が労災の認定を受けている。
■自殺は「業務に原因」/出向の会社員めぐり判決
共同通信によると、福岡県内の子会社に単身で出向中に自殺した兵庫県の会社員=当時(48)=について、福岡地裁は
12日、「自殺は業務が原因」と認定し、労災と認めなかった労働基準監督署の処分を取り消す判決を言い渡した。
裁判長は「出向や子会社での業務、残業時間などを総合すると、精神疾患を生じさせる心理的負荷になった可能性がある」と述べた。
判決によると、大阪市の設計会社の社員は
1999年8月、福岡県筑後市にある子会社に単身赴任。不慣れな担当業務や長時間の勤務でうつ病か適応障害になり、同年12月、会社の倉庫で首つり自殺した。
妻が労災申請したが、八女労基署(福岡県八女市)は2001年9月、「自殺は業務が原因ではない」として、遺族補償年金と葬祭料を支払わなかった。審査請求した福岡労働局や労働保険審査会(東京)も「死に至るほどの心理的負荷はなかった」と棄却。妻が提訴していた。
■介護で寄り道は「通勤」/休業補償の不支給取り消し
共同通信によると、義父の介護のために寄り道した後、帰宅する途中に交通事故に遭ったのは通勤災害だとして、大阪府の男性が、休業補償を不支給とした労働基準監督署長の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は
12日、請求を認めて支給を命じた。
通勤経路を外れたことが日常生活上、必要な行為だったかどうかなどが争点となり、裁判長は判決理由で、介護の内容を具体的に検討。両足が不自由な義父と同居する義兄の帰宅が遅く、男性が週4日程度介護していたことなどから「必要不可欠な行為」と認め、決定を取り消した。
判決によると、男性は
2001年2月26日、建材店での勤務を終え、通勤経路とは異なる市内の義父宅へ向かった。夕食の準備などの介護をした後、徒歩で帰宅途中に交差点でミニバイクと衝突、脳挫傷などのけがをした。2003年2月に休業補償の支給を労基署長に請求したが翌3月、不支給の決定を受けた。
■違法残業で送検/労基署、社員の脳梗塞で
共同通信によると、大手機械メーカーが男性社員(39)に長時間にわたる違法な残業をさせたとして、東京労働局の上野労働基準監督署は
30 日、労働基準法(法定労働時間)違反の疑いで、法人と男性の管理監督責任者の部長(56)を東京地検に書類送検した。
男性は昨年2月下旬、脳梗塞を発症し、療養中。過労で労災と認定された。長時間労働による過労を発端に上場企業が書類送検されるのは異例。
調べによると、男性社員は子会社から東京本社に出向。農業施設事業部(東京都台東区)に所属し、農業用機械設置工事の現場監督をしていた。昨年2月1日から
26 日にかけ、男性に法定労働時間を超えて約 160 時間の違法な残業をさせた疑い。
法人によると、この男性は昨年2月に 200 時間を超える残業をしていたほか、同年1月にも 100
時間を超える残業をしていた。
法人では出向社員の労働時間を管理する仕組みがなく、男性の労働時間を把握していなかったという。同社は書類送検を受け、出向社員も含め労働時間の管理方法を改善し徹底する、としている。
■賃金格差の訴訟が和解/名古屋高裁
共同通信によると、総合職や事務職のコース別の待遇による男女の賃金格差は不当として、鉄鋼商社の社員(57)と元社員(63)の女性二人が差額賃金など計約1億円や総合職の地位確認を求めた訴訟が
20 日、高裁で和解した。
和解条項で、同社は二人に解決金を支払い、今年6月から女性社員を事務職から総合職に変更するなどとした。
名古屋地裁は 2004 年 12
月の判決で、差額賃金や総合職への変更の請求は退けたが、同社が「性差別をされない人格権を侵害した」などとして、現社員の女性への慰謝料と弁護士費用計 550
万円を認めていた。
■週末帰任は「通勤」、労基署の不支給取り消す/単身赴任で高裁
共同通信によると、日曜日に単身赴任先へ移動中の男性=当時(41)=が事故死したのは通勤災害として、妻(46)が遺族給付などを不支給とした労働基準監督署の処分を取り消すよう求めた訴訟の控訴審判決で、高裁の青山は
、「(単身赴任者の)週末帰宅型の通勤」として、請求を認めた一審判決を支持、労基署側の控訴を棄却した。
遺族給付を定めた労災補償保険法は4月に改正法が施行され、自宅から単身赴任先に戻る途中の事故も通勤災害と認められる。今回の判決は一審と同様、法改正を先取りした形で、妻の弁護士は「二審も同様に通勤災害を認めたのは初めて」としている。
裁判長は判決で、通勤とは「住居と就業の場所の間を合理的な経路と方法で往復すること」などと指摘。
男性が都合の良い列車がないため、自家用車で約3時間半かけて日曜日に移動した点を「健康と安全のためにやむを得ない」とした。
その上で、社宅は勤務していた生命保険会社の営業所の2階にあり「就業の場所と同一視できる」と位置付け「事故は(自宅と就業場所を往復する)週末帰宅型通勤の途中に発生した」と結論付けた。
判決によると、男性は日曜日の 1999
年8月1日夕、自宅から約3時間半離れた岐阜県の赴任先に車で出発。約4カ月後、途中の同県中津川市の沢に車ごと転落、死亡しているのが見つかった。 妻は 2001 年3月、遺族給付などを求めたが、同労基署は同8月、不支給処分とした。
■「試合が原因の可能性」 職員急死で最高裁差し戻し
共同通信によると、心臓に持病があった教育委員会の職員=当時(44)=が、教委が共催するバレーボール大会で急死したことが公務上の災害にあたるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が、最高裁第二小法廷で言い渡された。
裁判長は「試合前まで日常生活や運動ができており、出場による負荷が持病を悪化させた可能性がある」と判断。公務と死亡が無関係とした二審福岡高裁宮崎支部判決を破棄し、審理を福岡高裁に差し戻した。
差し戻し審では死亡原因についての審理がやり直され、公務上災害を主張した遺族側が勝訴する可能性が高い。
判決によると、 1990
年に教職員バレーボール大会で負傷した選手に代わり試合に出場、第2セット終了後に倒れ、約1時間後に急性心筋梗塞で死亡した。
一審鹿児島地裁判決では遺族側が勝訴したが、二審判決は「持病が悪化していた自然経過の中でたまたま競技が契機となった」と判断。「公務外」とした地方公務員災害補償基金鹿児島県支部の判断を正当と認め、一審判決を取り消した。
■組合側の再審査申立てを棄却/エッソ石油(名古屋)事件で中労委
エクソンモービルが名古屋管理事務所を閉鎖して組合員を転勤させたことなどが不当労働行為だとして救済申立てがあった事件で、中央労働委員会は3日、労組側の再審査申立てを棄却する命令書を交付した。管理事務所の閉鎖(組織変更)は経営政策上の判断であり、転勤させる業務上の必要性についても労組と誠実に団交を行っていたなどの判断を示した。
■勤務医の「過労死」認定/長時間労働認め公務災害
共同通信によると、地方公務員災害補償基金北九州市支部の審査会は
13
日までに、北九州市立医療センターの内科部長が、くも膜下出血で死亡したのは長時間労働による過労死だったとする請求を認めた。死は「公務外」で過労死ではないとしていた同基金北九州市支部長の認定を取り消した。
代理人の松丸正弁護士は「勤務医の過労死認定は全国でも数件。長時間労働を強いられている勤務医の勤務条件見直しにつながれば」と話している。
裁決は2月9日付。それによると、審査会はこの時間外労働について、倒れる前1カ月間は週平均 25
時間、前6カ月間は同 20 時間だったと認め、仕事の肉体的、精神的負荷などから「病気は公務に起因する」と過労死を認めた。
裁決書によると 2001
年6月、肝臓がん患者の治療直後にくも膜下出血で倒れ死亡した。同年7月に同基金北九州市支部長に公務災害認定を請求したが、支部長は 04 年 12
月に公務外と認定。これを不服として 05 年2月、北九州市支部審査会に審査請求をしていた。
■最高裁判決 勤務中にメール 「解雇は妥当」か゜確定
職場のパソコンで出会い系サイトに登録し、勤務中に大量のメールを送受信したとして、勤務先の福岡県内の専門学校を懲戒解雇された元教師の男性が、地位確認などを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(滝井繁男裁判長)は20日、男性の上告を退ける決定を出した。解雇を無効とした1審判決を取り消し、男性の請求を棄却した2審判決が確定する。
2審判決によると、男性のパソコンには98年9月以降、約3000件の受送信記録があり、うち800件以上が出会い系サイトや女性が相手で、男性は03年9月に懲戒解雇された。
1審は「授業をおろそかにしていた実態はなく、懲戒解雇は過酷」と男性の訴えを認めたが、2審は「職務専念義務に違反し、その程度も相当に重い」と判断した。(毎日新聞)
■二審も元従業員側が勝訴
共同通信によると、愛知県の紡績会社が一方的に紡績事業を廃止し解雇したとして、紡績部門で勤務していた男女計百人が、従業員の地位確認と未払い賃金の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁
17 日、元従業員側の請求を認めた一審名古屋地裁判決を支持、会社側の控訴を棄却した。
原告側代理人によると、判決が確定すれば、支払われる賃金の総額は約8億 9,700
万円で、解雇をめぐる訴訟では戦後最大になるという。
判決理由で「同社は従業員らに相談せず民事再生手続きを決め、労組との交渉で紡績事業を続けると明言したのに翻した」とする一審の事実認定を引用。解雇の回避努力や必要性の検討も認められず「解雇を正当化する要素は見いだせない」とした。
判決などによると、紡績会社は 1951 年に紡績事業を始め、中部地方では大手に成長した。しかし繊維不況で
2000 年 10 月、民事再生法の適用を申請。同年 11 月に紡績事業の廃止を原告に通知し、翌 12 月から 01 年2月にかけて解雇した。
紡績会社は「担当者が不在でコメントできない」としている。
■サービス残業で「慰労金」2億4000万円支給
ホームセンター大手が、従業員にサービス残業をさせていた可能性があるとして、従業員の約9割の1084人に2億4390万円を支払っていたことが分かった。
昨年9月、北九州市内の3店舗で残業代を一部支払わなかったとして北九州東労働基準監督署から労働基準法違反容疑で書類送検された。同社は労基署の調査開始後に、全店舗(当時約150店)の従業員を対象に2002年度と03年度のサービス残業の調査を実施。その結果、約1億5000万円の申告があった。
同社は管理職の店長らの額も算定して加え、対象の1084人に均等に22万5000円を「勤務慰労金」として支給した。
同社は「サービス残業が実際にあったかどうかは分からないが、勤務時間の管理が甘かったのは事実。反省の意味も込めて慰労金を支払うことにした」としている。
(共同通信)
…【このような事件ばかりです。大企業であればサービス残業代を一括で支払うこともできますが、中小企業の場合は資金繰りの悪化に直結するリスクを負うことになります。もしサービス残業をさせているのであれば、業務の中身・勤務時間に無駄がないか等の労務管理の修正・見直しをすることをおすすめします。】
■サービス残業、総額21億円支給へ
某銀行は12日、2003年10月から05年9月の間に、派遣社員らを含むほぼすべての行員約4600人に賃金不払い残業(サービス残業)があったと発表した。
未払いとなっている総額約21億円、1人平均約45万円を1月中に支給する。
昨年10月、サービス残業是正などを目指し各企業を調査している労働基準監督署から指導を受け、労働債権が時効にならない過去2年間にさかのぼって、時間外労働の実態を調査。職場のパソコンを起動・終了した時間の記録などをもとに実態に近い就業時間を各行員に自己申告させたところ、1人平均月10時間程度がサービス残業になっていたことが分かった。
…【実際には10時間ということはあり得ないでしょう。少なくともこの4倍以上はサービス残業があると推測されます。】
同行では各職場の管理職が部下の就業時間を毎日把握し、記録する制度になっている。だが、上司に事前申告した時間より残業が長引いても、記録の修正が漏れていたケースもあり、未払いが生じた。同行は「時間管理に甘さがあった。始業・終業時間の確認方法を徹底する」としている。
…【現在は、タイムカードの導入を労働基準監督署から指導されるケースが多い傾向にあります。銀行がタイムカードを導入していないのは時間管理が甘すぎると言っても過言ではないでしょう。コンプライアンスとは名ばかりです。】
各労基署の指導強化もあり、サービス残業の判明件数は増加傾向にある。全国では某電力で約69億円、人材派遣会社で約54億円、某電力で約23億円などの未払いが発覚している。
(読売新聞)
■800万円支払いで和解:男女の賃金格差めぐる訴訟…H17.12
共同通信によると、男女間の賃金格差は違法として、女性Aさんが、会社に約 2,300
万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審は、会社が解決金 800 万円を支払うことで大阪高裁(島田清次郎裁判長)で和解が成立した。
2001 年 の一審京都地裁判決は「女性であることを理由にした差別」とし、会社に計 670
万円の支払いを命じていた。
原告側代理人は「実質的な勝訴。差別の是正を求めた意義のある判断だ」と話した。一審判決によると、女性Aさんは 1981
年に入社。同期の男性と初任給で約 7 万円の差があり、差額は 11 年間で約 1,400 万円に上った。
今年 11
月の結審時、高裁が和解を勧告した。会社は「担当者がいないのでコメントできない」としている。
■契約社員の解雇無効…H17.12
業務の外注化を理由に雇用期間終了前に解雇したのは違法として、元契約社員の5人が、会社に地位確認などを求めた訴訟は、ネスレ側が解雇を撤回し、解決金を支払うことで高裁で和解が成立した。
今年3月の地裁判決は、解雇を無効とし、会社側に月額約 12 万〜 17
万円の未払い賃金支払いなどを命じていた。5人は退社する。解決金の額は双方とも明らかにしていない。
一審判決によると、5人は支店に勤務し、1992 年以降、スーパーの店頭などで食品の販売促進業務をしていたが、2003
年に業務外注化を理由に解雇を通知された。
労働者側は「全面勝訴の和解内容で満足している」、会社側は「和解内容について申し上げられない」としている。
【解雇と言えばトラブルがつきものです。一方的な力任せの解雇では労使ともに時間・労力を消費し、結果的に会社側が負けるケースが多く見受けられます。これからの時代はますますトラブルが増えることが予想されますので、最低限会社の規程ぐらいは整備しておかなくてはなりません。】
■賃金不払い残業の電話相談に1,247件…H17.11.23
厚生労働省では賃金不払い残業解消に関する全国一斉の電話相談を23日の勤労感謝の日に実施した。相談件数は1,247件(労働者本人893件、労働者の家族288件、使用者13件)で、このうち賃金不払残業に関する相談は852件にのぼっている。371件は時間外労働の手当が一切支払われていないというものだった。業種別では商業(287件)、製造業(244件)が多い。
■2年間で残業代など約14億円未払い…H17.10.28
某企業は10月28日、2003年10月〜05年9月の2年間に、間接部門従事者など約1,700人に対して時間外・休日労働、深夜割増分の総額約14.2億円が未払いだった【未申告が確認された時間外および休日労働時間
約687,000時間】ことを発表した。
調査は労働基準監督署から指導を受けたことを踏まえ実施したもの。未払い分を対象者に支払うことになった。
【適正な労働時間管理の徹底を含めたコンプライアンス(事業活動に伴う関係諸法令の遵守)への取り組みができていない例で、一般企業でしたら資金繰りに行き詰ることにもなりかねません。賃金体系をチェックし、問題があるようてしたら上記のようなことが起きないよう対策を練ることをおすすします。】
■うつ病で自殺、労災と認定 会社が厳しい叱責で圧迫
共同通信によると、大手企業の所長だった男性がうつ病で自殺したのは、過大な売り上げ目標を達成できず上司からどう喝的なしっ責を受けた心理的な圧迫が原因などとして、労働基準監督署は労災と認定した。
代理人の弁護士によると、男性は 2003
年4月、営業成績の著しく悪い営業所の所長になった。営業所を統括する地方支店の上司は毎日早朝に「その日の工事出来高予定」を報告させ、厳しいしっ責を続けた。
さらに自殺直前の会議では、支店の上司らから「能力がない」「会社を辞めろ」「会社を辞めても楽にはならないぞ」などと約2時間にわたり、ののしられた。男性は
2004 年8月にうつ病を発症。翌月、営業所敷地内で首つり自殺した。
男性は 2004
年8月以降、午前6時半ごろ出勤し、午後8時半ごろ退社する長時間労働が続いたが、出勤簿には午前8時出勤、午後6時退社と記載することを強制されていた。また会社と下請け業者との間で板挟みになり、業者への工事代金
150万円の支払いを個人の預金から立て替え払いしていた。
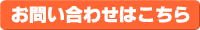 |
|