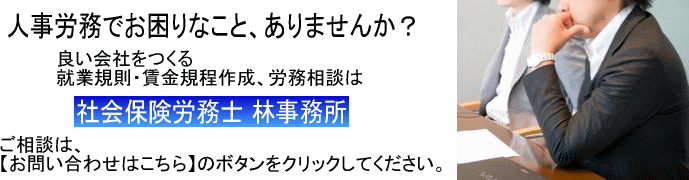|
|
【緊急情報です、お知らせいたします!】
■1ヶ月残業時間が60時間を超える場合、残業代割増率が25%から50%に増加
|
 |
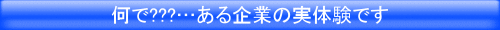
従業員の親が、「こんなに残業させてもいいのか?」と会社に申し出てきました。
その数日後、労働基準監督署から会社に調査の連絡が入ったのです。
会社の状況を見てみると、
 退職した社員の月平均残業は約80時間でした。そして 退職した社員の月平均残業は約80時間でした。そして
 残業代は全く払っていない。 残業代は全く払っていない。
 就業規則は作っていない。 就業規則は作っていない。
 労働契約書も交わしていない。 労働契約書も交わしていない。
 残業をさせるために届出をしなければならない「時間外・休日労働に関する協定書」を労働基準監督署に出していない。 残業をさせるために届出をしなければならない「時間外・休日労働に関する協定書」を労働基準監督署に出していない。
法令遵守(コンプライアンス)が散々叫ばれている時代、これだけ労働基準法を守っていないと、どんなに専門知識を持っていてもお手上げです。
会社を救うことはできません。
労働基準監督署は6ヶ月分の残業代を支払うよう指導しました。
給与が25万円の退職者でしたので、このケースの場合80時間残業で約90万円の支払です。
社長は怒っていました。
「こんなことになるとは…」
しかし、6ヶ月分で済んだのでよかったのです。
 残業代は2年まで遡れます。 残業代は2年まで遡れます。
2年分の残業代を支払えといわれていたら約360万円の支払だったのです。
 仮に10人の従業員が労働基準監督署に相談に行っていたら 仮に10人の従業員が労働基準監督署に相談に行っていたら
約3600万円になったかもしれないのです。
この某企業の経営者は人情のある社長でした。
昔は経営者の人情、面倒見のよさでそれほどトラブルも無かったようです。
しかし、今は時代が変わりました。
人情・面倒見のよさだけでは通用しないのです。
社員も在職中にいろいろと考えています。
「この会社は入社してみたけど、求人情報と書いてあることが違う。残業代も出ないし法律に違反している。社会保険も入っていない。やるべきことをしていない企業だ。」
企業はやるべきことをしていない、だから社員は働かない。
そして、お互いが「オマエが悪い」と言い合うことになるという悪循環になりトラブルが起こります。
企業は労働基準監督署に訴えられた時に気づくのです。
「社員を守る法律は様々あるが、会社を守る法律はない」と。
そして嫌な思いをするのです。
マイナスの出来事なので、かなりのストレスが溜まります。
そして大概は続けて2度3度と連続して訴えが起こるケースがほとんどです。
それは、社員や退職者が連絡を取り合って情報交換しているからです。
また嫌な思いをし、かなりのストレスがたまり、
残業代をまとめて支払い資金繰りが厳しくなっていくのです。
給与明細を修正し、源泉所得税を修正し、面倒な事務が増えるばかりです。
事務員も法律違反を目のあたりにして、業務に対するモチベーションが下がり、
会社の悪いイメージが頭に焼きつきます。
なんと非効率なことが起こるのでしょう!
この某企業は給与の決め方も適当でした。
社長の気分で彼は「25万円」ね、彼は「30万円」ねという感じで。
給与規程もなくどんぶり勘定でした。
このどんぶり勘定できめていた給与も残業代の単価を多くする要因の1つでした。
 【結論】 【結論】
たくさんの残業をさせるなら、残業代をキッチリ支払う。
あるいは残業を減らす対策を考えて実行する。
そのためには就業規則、賃金規程の見直し、改訂が必要です。
下記に会社が得する【残業対策】
を載せましたので、ぜひ取り組んでみてください!!!
|
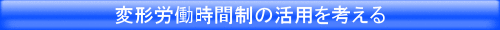
変形労働時間制は、就業形態の多様化に対応するためのものであり、週休2日制の採用、年間休日日数の増加、業務の繁閑に応じた労働時間の配分について、労働時間を短縮を工夫して進めていくことを容易にするためのものです。
変形労働時間の導入で、会社の残業や休日出勤が減らせる可能性が出てきます。要するに、無駄な残業代・休日出勤代の支払いが減るのです。
労働基準法では、下記の4種類の変形労働時間制が認められています。
● 1ヵ月単位の変形労働時間制
1ヵ月単位の変形労働時間制とは、1ヵ月以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下の範囲内において、特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度のことをいいます。
例えば、1ヵ月のうち、月末に業務が集中する会社や職場で利用しやすい制度で、1ヵ月以内の一定の期間の中で、月末に比較的長い所定労働時間を組み、休日も少なくなる代わりに、月初めには休日を多く、所定労働時間も短くすることで労働時間を短縮しようとするものです。
● 1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制とは、季節により業務に繁閑のある事業場において、繁忙期に長い労働時間を設定し、かつ、閑散期に短い労働時間を設定することにより効率的に労働時間を配分して、年間の総労働時間の短縮を図ることを目的に設けられたものであり、労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、1年以内の一定期間を平均し1週間の労働時間を40時間以下の範囲内にした場合、特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度のことをいいます。
●フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、1ヵ月以内の一定期間(清算期間)の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定して働く制度です。
フレックスタイム制を採用するには、1.就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることを規定すること。2.労使協定において、対象となる労働者の範囲、清算期間(1ヵ月以内)、清算期間中の総労働時間(清算期間中の法定労働時間の範囲内)、1日の標準労働時間などを定めることが必要です。
●1週間単位の非定型的変形労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じることが多く、かつ、定型的に定まっていないため就業規則等により各日の労働時間を特定することが困難な事業(常時使用する労働者が30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業)において、労使協定に基づき、前週末までに翌週の各日の労働時間を労働者に書面で通知することにより、1週40時間の範囲内で1日10時間まで労働させることができる制度です。
また、下記のような制度もあります。
●事業場外労働のみなし労働時間制
営業職など専ら事業場外で労働する労働者には、使用者の具体的な指揮が及ばず、労働時間の算定が困難な業務については 原則として
①その業務に要する労働時間を所定労働時間とみなます。
【例】
所定労働時間が8時間の事業場で、午前中は事業場内で勤務し、午後から事業場外で業務に従事した場合において、その事業場外での勤務時間が明確に把握できないときには、その日の全体としての労働時間が算定できないことになりますが、そのような時には、事業場内で業務に従事した時間を含め、全体として所定労働時間の8時間を勤務したものとみなすということです。
②その業務を遂行するためには、通常、所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、その業務に通常必要となる時間労働したものとみなす ことができます。
上記②の場合に、労使協定で定めた時間があれば、労使協定で定めた時間とすることができ、この時間が法定労働時間を超える時は、所轄労働基準監督署長へ届け出なければなりません。
【例】
ある事業場におけるセールスの業務については、8時間30分かかることもあれば、9時間30分かかることがあるとしても各日、各労働者が当該セールスの業務の遂行に通常必要とされる時間は、客観的に判断すると9時間であることから、当該セールスの業務に従事した場合は9時間労働したものとみなすこととするものです。
労働時間の一部を事業場外で業務に従事した場合
【例】
事業場外での業務に通常の状態で客観的に必要とされる時間が6時間であれば、事業場内で労働した時間が3時間である日には9時間、4時間である日に10時間労働したものとみなされます。
なお、事業場外労働のみなし労働時間制の対象労働者も、休憩、法定休日に関する規定や深夜業の割増賃金の規定は、原則どおり適用されます。
■1ヶ月残業時間が60時間を超える場合、残業代割増率が25%から50%に増加
 就業規則・賃金規程の見直しは必要ありませんか? 就業規則・賃金規程の見直しは必要ありませんか?
|
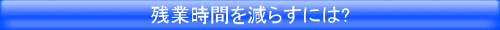
残業を減らせば、社会保険料を削減できるケースが多々あります。
残業による従業員の不平不満やストレスを解消でき、無用な労使トラブルを減らすことができます。
オンオフのメリハリがつき、従業員が活き活きと働く要因の1つにもなります。
無駄に居残りされると会社にとっては良いことは1つもナシ!
さて、どうすれば残業は減らせるのでしょうか?
残業短縮が遅れている要因例
・社内に残業短縮に対する意識が低い
・生産制の向上が十分に進んでいない
・残業など日常的な管理が不十分

企業の実情に即した残業短縮対策の検討例
・残業短縮目標の設定、意識改革の推進
・残業短縮のための業務改善、生産性向上対策の検討
・完全週休2日制の導入、週40時間労働制の導入による法令遵守の模索
・変形労働時間制、フレックスタイム制導入の検討
 【取り組み方】 【取り組み方】
①経営者の決断
②残業短縮推進体制の確立
③現状把握
(1)1日・1週間・1ヵ月・季節および1年間の労働時間、年次有給休暇の取得などの実態の把握
(2)業務内容の実態調査
1日・1週間・1ヵ月・季節および1年間の把握
④実施計画の作成
上記を参考に残業対策を行うとよいでしょう。
■■残業削減に使える主な方法■■
労働条件の引き下げについて
労働条件の引き下げには、労働契約の不利益変更に該当し、社員の個別の同意なしに会社側からの一方的な変更は認められません。
就業規則で記載内容を変更することで労働条件を引き下げられる場合も社員の同意が必要になりますが、この場合は社員個別の同意ではなく、過半数社員の代表の同意で就業規則を変更するころが可能です。
一方、社員の労働条件が向上する、または今までと変わらない場合は、過半数社員の代表の意見を聴取するだけで就業規則の変更ができます。
●労働時間の見直しをする
タイムカード・賃金台帳をもとに、1日・1週間・1ヵ月・季節および1年間の労働時間、年次有給休暇の取得などの実態の把握します。
特に1ヶ月の労働時間・残業時間と残業代の把握が重要です。
●固定残業代を導入する
毎月の残業代を固定して支給します。残業時間の計算も省け、給与計算事務の省力化にもなります。
例えば20時間の残業代として50,000円を固定支給するとしても、実労残業時間が20時間を超えてしまった場合は、その超過時間分の残業代を別途支払う必要があります。また、20時間を超えなかった場合であっても、50,000円を固定支給しなければなりません。
残業時間などを分析しないで固定残業代を導入いすると、残業代は増えるケースも出てきます。。しかし、基本給の一部を固定残業代にしてしまうことができれば、残業代が大幅に削減されることになります。
ただし、この方法は支払の内訳を変更しただけであり、基本給の減額につながるので、労働条件の不利益変更に該当します。
したがって従業員の個別同意を得ておかなければならず、また次の要件を満たす必要があります。
①就業規則において、賃金(基本給や手当)に、時間外労働、深夜労働、休日労働の割り増し賃金を含むことを明記すること
②労働契約書、労働条件通知書、辞令などで、従業員に賃金に含まれる残業代部分が明確に区分して示されていること
③賃金を含めたことにした時間数を超えた分については、別途差額を支払うこと
●交替制(シフト制)を検討してみる
工場や店舗、病院などでは24時間、365日無休で稼働しているところがあります。
このような場合は、通常勤務、準夜勤、夜勤といった具合に労働時間を分けて、複数の従業員を交替で働かせるようにします。このような働き方を交替勤務制(シフト制)といいます。
交替勤務制をうまく利用すると残業代が削減できます。1人が働く時間を8時間以内とし、その枠内でA、B、Cシフトといった具合にシフトを組んで労働時間を決めます。Aシフトの従業員が働き終えた後は、Bシフトの従業員が控えているわけですから、うまくシフトを組めば残業がまったく発生しません。1日8時間を超えた時間外労働は1.25倍の割増賃金の支払いが必要になることを考えれば、交替制にして効率よく人を活用したほうがいいでしょう。
シフト勤務制を導入する場合、1ヶ月単位の変形労働時間制や1年単位の変形労働時間制を活用して従業員1人当たりの労働時間が週40時間以内になるようにし、12時間勤務の2交代制度といった働かせ方も可能です。
ただし交替制にしたために人を増やすと社会保険料等の負担が増えます。人を増やさなければならないときは社会保険に加入義務のないパートやアルバイトをうまく活用するとよいでしょう。
●残業許可制を設ける
残業許可制とは、残業を行う従業員に事前に会社に許可を得させる制度です。
残業を行う従業員に、①残業で行わなければならない業務上の理由、②残業を行う業務内容、③残業予定時間数、を記入して会社に許可書を提出させます。
許可書の内容について、上司(管理職)が不必要と判断した場合は、残業を認めずに帰宅させるようにします。
こうすれば、従業員の残業をダラダラせずに、事前に管理することで残業代を削減することができます。
●ノー残業デーを設ける
1カ月の中で「特定の曜日」または「特定の日」を決めて、その日は残業を禁止する「ノー残業デー」をつくります。
ノー残業デーの導入単位は、課単位から部単位、全社一斉といろいろなパターンが考えられますが、この導入単位が大きくなれば残業代削減効果は大きくなります。
また、恒常的に残業をしている場合、従業員の疲労回復にも役立ちます。
●休日の振替を導入する
従業員を法定休日に出勤させた場合、会社は1.35倍の割増賃金を支払わなければなりません。しかし、業務上どうしても休日に労働させなくてはならないことがあります。こういうときは、事前に休日を振替える旨を本人に伝え、振替える日を指定して休日を入れ替えれば、休日に労働させても割増賃金を支払う必要がなくなります。
振替休日の導入方法
休日の振替をするときは、①就業規則に「業務の都合上必要なときは休日を振替える」旨の規定を書いておく必要があります。
そして、②振替を命じる社員に、前日までに振替えるべき日を特定して伝えます。
こうすることで休日と労働日の入れ替えが成立し、割増賃金の支払いが必要なくなります。
このときに注意することは、振替えるべき日を同一週内に指定することです。
他の週に指定すると、週の労働時間が法定労働時間(40時間)を超えてしまい
結局、割増賃金を支払わなければならなくなるからです。
●専門業務型裁量労働制を考える
業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者にゆだねる必要がある業務として、厚生労働省令及び大臣告示により定められた以下に掲げる19の専門業務の中から、対象となる業務を労使協定で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使協定で定めた時間労働したものとみなすことができます。
本制度を実施することにより、対象労働者については、実際の労働時間と関係なく、労使協定で定めた時間労働したものとみなす効果が発生します。
なお、専門業務型裁量労働制の対象労働者も、休憩、法定休日に関する規定や深夜業の割増賃金の規定は、原則どおり適用されます。
専門業務型裁量労働の対象とできる業務は、以下の19業務に限定されています。
・新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
・情報処理システムの分析又は設計の業務
・新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務
・衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
・放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
・広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
・事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
・建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
・ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
・有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
・金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
・学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る)
・公認会計士の業務
・弁護士の業務
・(一級、二級、木造)建築士の業務
・不動産鑑定士の業務
・弁理士の業務
・税理士の業務
・中小企業診断士の業務
制度の導入に当たっては、あらかじめ、過半数労働組合又は労働者の過半数を代表する者との労使協定により、専門業務型裁量労働制に関する協定届を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
また、この労使協定においては、いわゆる健康・福祉確保措置及び苦情処理措置を定める必要があります。
●企画業務型裁量労働制を考える
事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査、分析等の業務であって、業務の性質上これを適切に遂行するには、その遂行方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、業務の遂行の手段や時間配分の決定等に関し、使用者が具体的な指示をしないこととする業務(対象業務)で、以下の要件を満たした場合には、労使協定で定めた時間労働したものとみなすことができます。
本制度を実施することにより、対象労働者については、実際の労働時間と関係なく、決議で定めた時間労働したものとみなす効果が発生します。
なお、企画業務型裁量労働制の対象労働者も、休憩、法定休日に関する規定や深夜業の割増賃金の規定は、原則どおり適用されます。
労使委員会が以下の事項について、委員の5分の4以上の多数による合意により決議をし、企画業務型裁量労働制に関する決議届として、これを所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
また、使用者は、決議が行われた日から起算して6ヵ月以内に1回、企画業務型裁量労働制に関する報告を所轄労働基準監督署長へ届け出なければなりません。
1.対象業務
2.対象労働者の範囲
3.みなし労働時間 (1日あたりの時間数)
4.対象労働者の健康・福祉確保の措置
5.対象労働者の苦情処理の措置
6.労働者本人の同意の取得及び不同意労働者への不利益取扱いの禁止
7.決議の有効期間の定め (3年以内とすることが望ましい)
8.4.5.6.に関する労働者ごとの記録の保存 (期間満了後3年間)
労使委員会の要件は以下のとおりである。
1.委員の過半数については、過半数労働組合又は労働者の過半数を代表する者により任期を定めて指名されていること
2.委員会議事録の作成、保存(3年間)、労働者への周知をしていること
3.労使委員会の運営規程を定めていること
4.労使委員会の委員であること等を理由とした不利益取扱いを禁止すること
■1ヶ月残業時間が60時間を超える場合、残業代割増率が25%から50%に増加
 就業規則・賃金規程の見直しは必要ありませんか? 就業規則・賃金規程の見直しは必要ありませんか?
終身雇用が崩壊し、人情・面倒見のよさだけでは社員はついていきません。
対策をうつなら今がベストです。
|

1週間の労働時間が40時間と法律で義務付けられています。
労働時間を1日8時間と決めている場合には、週休2日制を導入することになります。
労働時間短縮の方法としては、週休2日制の導入による週休日の増加が効果的です。
 週休2日制のメリットとしては 週休2日制のメリットとしては
①従業員の定着率の向上と従業員のモラールの向上
②優秀な人材採用がしやすくなる
③労使トラブルの減少
④人事労務管理の見直しによる業務効率の向上など
経営上重要なものがあげられます。
 また、統計からも週休2日制の普及割合が高い業種ほど、 また、統計からも週休2日制の普及割合が高い業種ほど、
常用男子自己都合離職率、欠勤率、労働災害の度数率が低いという効果が見られます。
労働時間短縮は、疲労回復、健康増進、地域・社会活動の参加んどによる豊かな生活をもたらすだけでなく、企業にとっても健康で意欲にあふれた勤労がもたらされ、能率のよい仕事の遂行が容易となり、企業発展の原動力を得ることができます。
企業を一段階上に発展させるには、週40時労働制の遵守は必要不可欠です。活き活きと従業員が働くポイントの1つになります。
いくら立派な経営理念があっても、1週40時間労働制を導入できないようでは、従業員の定着と優秀な人材の確保は難しいでしょう。
なぜなら、「うちの会社は法令遵守をしていない」という目で従業員が見るからです。
そして、不払い残業をさせているようだと…
長時間働かせても、定着率の悪化、労使トラブルの増加、過労死の危険性、業務効率の停滞といいことはありません。
万が一過労死が起きたら大変!!!…過労死労災認定について一部記載します。
会社が殺人マシーン呼ばわりされないためにも・・・
|
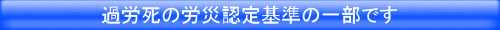
●長期間の過重業務について
(ウ) 過重負荷の有無の判断
…疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると、その時間が長いほど、業務の過重性が増すところであり、
…… 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、
業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断する…。
●労働時間以外の要因
不規則な勤務…予定された業務スケジュールの変更の頻度・程度、事前の通知状況、予測の度合、業務内容の変更の程度等
拘束時間の長い勤務…拘束時間数、実労働時間数、労働密度(実作業時間と手待時間との割合等)、業務内容、休憩・仮眠時間数、休憩・仮眠施設の状況(広さ、空調、騒音等)等
出張の多い業務…出張中の業務内容、出張(特に時差のある海外出張)の頻度、交通手段、移動時間及び移動時間中の状況、宿泊の有無、宿泊施設の状況、出張中における睡眠を含む休憩・休息の状況、出張による疲労の回復状況等
交替制勤務・深夜勤務…勤務シフトの変更の度合、勤務と次の勤務までの時間、交替制勤務における深夜時間帯の頻度等
作業環境…温度環境、騒音、時差
精神的緊張を伴う業務…【日常的に精神的緊張を伴う業務】業務量、就労期間、経験、適応能力、会社の支援等 【発症に近接した時期における精神的緊張を伴う業務に関連する出来事】 出来事(事故、事件等)の大きさ、損害の程度等
【参考】時間外労働と脳血管疾患・虚血性心疾患との関連について
時間外労働は、仕事による負荷を大きくするだけでなく、睡眠・休養の機会を減少させるので、疲労蓄積の重要な原因のひとつと考えられています。医学的知見をもとに推定した、時間外労働時間(1週当たり40時間を超える部分)と脳出血などの脳血管疾患や心筋梗塞などの虚血性心疾患の発症などの健康障害のリスクとの関連性を下表に示しますので参考にしてください。
|
時間外労働時間
|
月45時間以内
|
時間の増加とともに健康障害のリスクは徐々に高まる
|
月100時間または2~6か月平均で月80時間を超える |
|
健康障害のリスク
|
低い
|
高い
|
|
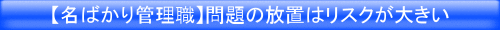
名ばかり管理監督者に対する通達がでました。これはおそらく社会問題となっている小売・飲食から通達を出したということだと思いますが、他の業界にもこの通達が一つの基準になるでしょう。
 また、通達が出たということは、小売・飲食業は急ぎ改善が必要になるということです。まずは基本をおさえてください。 また、通達が出たということは、小売・飲食業は急ぎ改善が必要になるということです。まずは基本をおさえてください。
●管理監督者の条件
1 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること
労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあり、労働時間等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していなければ、管理監督者とはいえません。
2 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること
労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあるというためには、経営者から重要な責任と権限を委ねられている必要があります。「課長」「リーダー」といった肩書きがあっても、自らの裁量で行使できる権限が少なく、多くの事項について上司に決裁を仰ぐ必要があったり、上司の命令を部下に伝達するに過ぎないようなものは管理監督者とはいえません。
3 現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること
管理監督者は、時を選ばず経営上の判断や対応が要請され、労務管理においても一般労働者と異なる立場にある必要があります。労働時間について厳格な管理をされているような場合は、管理監督者とは言えません。
4 賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること
管理監督者は、その職務の重要性から、定期給与、賞与、その他の待遇において、一般労働者と比較して相応の待遇がなされていなければなりません。
●名ばかり管理監督者に対する通達
「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について(基発第0909001号)」
この通達は、、多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗の店長等の管理監督者性の判断に当たっての特徴的な要素について、店舗における実態を踏まえ、最近の裁判例も参考としてまとめたものとなっています。
具体的には、次の通り判断基準を示しています。
1 「職務内容、責任と権限」についての判断要素
店舗に所属する労働者に係る採用、解雇、人事考課及び労働時間の管理は、店舗における労務管理に関する重要な職務であることから、これらの「職務内容、責任と権限」については、次のように判断されるものであること。
(1) 採用
店舗に所属するアルバイト・パート等の採用(人選のみを行う場合も含む。)に関 する責任と権限が実質的にない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。
(2) 解雇
店舗に所属するアルバイト・パート等の解雇に関する事項が職務内容に含まれてお らず、実質的にもこれに関与しない場合に、管理監督者性を否定する重要な要素と なる。
(3) 人事考課
人事考課(昇給、昇格、賞与等を決定するため労働者の業務遂行能力、業務成績等 を評価することをいう。以下同じ。)の制度がある企業において、その対象となって いる部下の人事考課に関する事項が職務内容に含まれておらず、実質的にもこれに関与しない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。
(4) 労働時間の管理
店舗における勤務割表の作成又は所定時間外労働の命令を行う責任と権限が実質的 にない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。
2 「勤務態様」についての判断要素
管理監督者は「現実の勤務態様も、労働時間の規制になじまないような立場にある者」 であることから、「勤務態様」については、遅刻、早退等に関する取扱い、労働時間に 関する裁量及び部下の勤務態様との相違により、次のように判断されるものであること。
(1) 遅刻、早退等に関する取扱い
遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされ る場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。
ただし、管理監督者であっても過重労働による健康障害防止や深夜業に対する割増 賃金の支払の観点から労働時間の把握や管理が行われることから、これらの観点から 労働時間の把握や管理を受けている場合については管理監督者性を否定する要素とは ならない。
(2) 労働時間に関する裁量
営業時間中は店舗に常駐しなければならない、あるいはアルバイト・パート等の人員が不足する場合にそれらの者の業務に自ら従事しなければならないなどにより長時 間労働を余儀なくされている場合のように、実際には労働時間に関する裁量がほとんどないと認められる場合には、管理監督者性を否定する補強要素となる。
(3) 部下の勤務態様との相違
管理監督者としての職務も行うが、会社から配布されたマニュアルに従った業務に 従事しているなど労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を 占めている場合には、管理監督者性を否定する補強要素となる。
3 「賃金等の待遇」についての判断要素
管理監督者の判断に当たっては「一般労働者に比し優遇措置が講じられている」など の賃金等の待遇面に留意すべきものであるが、「賃金等の待遇」については、基本給、
役職手当等の優遇措置、支払われた賃金の総額及び時間単価により、次のように判断されるものであること。
(1) 基本給、役職手当等の優遇措置
基本給、役職手当等の優遇措置が、実際の労働時間数を勘案した場合に、割増賃金 の規定が適用除外となることを考慮すると十分でなく、当該労働者の保護に欠けるお それがあると認められるときは、管理監督者性を否定する補強要素となる。
(2) 支払われた賃金の総額
1年間に支払われた賃金の総額が、勤続年数、業績、専門職種等の特別の事情がないにもかかわらず、他店舗を含めた当該企業の一般労働者の賃金総額と同程度以下である場合には、管理監督者性を否定する補強要素となる。
(3) 時間単価
実態として長時間労働を余儀なくされた結果、時間単価に換算した賃金額において、 店舗に所属するアルバイト・パート等の賃金額に満たない場合には、管理監督者性を 否定する重要な要素となる。
特に、当該時間単価に換算した賃金額が最低賃金額に満たない場合は、管理監督者性を否定する極めて重要な要素となる。
■参考■
管理監督者についての条文及び通達
● 労働基準法(昭和22 年法律第49 号)(抄)
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第41 条この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定 は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一(略)
二事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三(略)
● 管理監督者の範囲についての解釈例規
監督又は管理の地位にある者の範囲
(昭和22 年9 月13 日付け発基17 号、昭和63 年3月14 日付け基発150 号)
法第41 条第2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」とは、一般的には、 部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者 の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。具体的な判断にあたつては、下記の考え方によられたい。
記
(1) 原則
法に規定する労働時間、休憩、休日等の労働条件は、最低基準を定めたものである から、この規制の枠を超えて労働させる場合には、法所定の割増賃金を支払うべきこ とは、すべての労働者に共通する基本原則であり、企業が人事管理上あるいは営業政 策上の必要等から任命する職制上の役付者であればすべてが管理監督者として例外 的取扱いが認められるものではないこと。
(2) 適用除外の趣旨
これらの職制上の役付者のうち、労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超え て活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様 も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限つて管理監督者として法 第41条による適用の除外が認められる趣旨であること。従つて、その範囲はその限 りに、限定しなければならないものであること。
(3) 実態に基づく判断
一般に、企業においては、職務の内容と権限等に応じた地位(以下「職位」という。) と、経験、能力等に基づく格付(以下「資格」という。)とによつて人事管理が行わ れている場合があるが、管理監督者の範囲を決めるに当たつては、かかる資格及び職 位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要が あること。
(4) 待遇に対する留意
管理監督者であるかの判定に当たつては、上記のほか、賃金等の待遇面についても 無視し得ないものであること。この場合、定期給与である基本給、役付手当等におい
て、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要があること。なお、一般労働者に比べ優遇措置
が講じられているからといつて、実態のない役付者が管理監督者に含まれるものではないこと。
■1ヶ月残業時間が60時間を超える場合、残業代割増率が25%から50%に増加
 就業規則・賃金規程の見直しは必要ありませんか? 就業規則・賃金規程の見直しは必要ありませんか?
終身雇用が崩壊し、人情・面倒見のよさだけでは社員はついていきません。
対策をうつなら今がベストです。
|
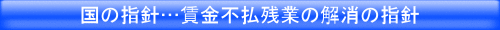
 国は賃金不払残業の解消に力を注いでいます。そして、働く人たちもこのあたりは敏感になってきています。法改正前に企業としてきちんとした対策をとらなければならない時期にきています。 国は賃金不払残業の解消に力を注いでいます。そして、働く人たちもこのあたりは敏感になってきています。法改正前に企業としてきちんとした対策をとらなければならない時期にきています。
指針を紹介いたします。
■■賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針について■■
●賃金不払残業の解消
賃金不払残業(所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせること。)は、労働基準法に違反するものであり、その解消を図るために、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」(平成13年4月6日付け基発第339号)が示され、使用者に適正に労働時間を管理する責務があることを改めて明らかにするとともに、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置等を具体的に示しています。
しかしながら、未だ労働時間の把握に係る自己申告制(労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの。)の不適正な運用など使用者が適正に労働時間を管理していないことを原因とする割増賃金の不払いなどの状況もみられるところです。
このため、事業場における賃金不払残業の実態を最もよく知る立場にある労使に対して主体的な取組を促すとともに、適正な労働時間の管理を一層徹底し、賃金不払残業の解消を図る必要があります。
賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針(平成15年5月23日付け基発第0523004号)
趣旨
賃金不払残業(所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせること。以下同じ。)は、労働基準法に違反する、あってはならないものである。
このような賃金不払残業の解消を図るためには、事業場において適正に労働時間が把握される必要があり、こうした観点から、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき基準」(平成13年4月6日付け基発第339号。以下「労働時間適正把握基準」という。)を策定し、使用者に労働時間を管理する責務があることを改めて明らかにするとともに、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置等を具体的に明らかにしたところである。
しかしながら、賃金不払残業が行われることのない企業にしていくためには、単に使用者が労働時間の適正な把握に努めるに止まらず、職場風土の改革、適正な労働時間の管理を行うためのシステムの整備、責任体制の明確化とチェック体制の整備等を通じて、労働時間の管理の適正化を図る必要があり、このような点に関する労使の主体的な取組を通じて、初めて賃金不払残業の解消が図られるものと考えられる。
このため、本指針においては、労働時間適正把握基準において示された労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置等に加え、各企業において労使が各事業場における労働時間の管理の適正化と賃金不払残業の解消のために講ずべき事項を示し、企業の本社と労働組合等が一体となっての企業全体としての主体的取組に資することとするものである。
●労使に求められる役割
(1) 労使の主体的取組
労使は、事業場内において賃金不払残業の実態を最もよく知るべき立場にあり、各々が果たすべき役割を十分に認識するとともに、労働時間の管理の適正化と賃金不払残業の解消のために主体的に取り組むことが求められるものである。
また、グループ企業などにおいても、このような取組を行うことにより、賃金不払残業の解消の効果が期待できる。
(2) 使用者に求められる役割
労働基準法は、労働時間、休日、深夜業等について使用者の遵守すべき基準を規定しており、これを遵守するためには、使用者は、労働時間を適正に把握する必要があることなどから、労働時間を適正に管理する責務を有していることは明らかである。したがって、使用者にあっては、賃金不払残業を起こすことのないよう適正に労働時間を管理しなければならない。
(3) 労働組合に求められる役割
一方、労働組合は、時間外・休日労働協定(36協定)の締結当事者の立場に立つものである。したがって、賃金不払残業が行われることのないよう、本社レベル、事業場レベルを問わず企業全体としてチェック機能を発揮して主体的に賃金不払残業を解消するために努力するとともに、使用者が講ずる措置に積極的に協力することが求められる。
(4) 労使の協力
賃金不払残業の解消を図るための検討については、労使双方がよく話し合い、十分な理解と協力の下に、行われることが重要であり、こうした観点から、労使からなる委員会(企業内労使協議組織)を設置して、賃金不払残業の実態の把握、具体策の検討及び実施、具体策の改善へのフィードバックを行うなど、労使が協力して取り組む体制を整備することが望まれる。
■■労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について
労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかである。
しかしながら、現状をみると、労働時間の把握に係る自己申告制(労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの。以下同じ。)の不適正な運用に伴い、割増賃金の未払いや過重な長時間労働といった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況もみられるところである。
こうした中で、中央労働基準審議会においても平成12年11月30日に「時間外・休日・深夜労働の割増賃金を含めた賃金を全額支払うなど労働基準法の規定に違反しないようにするため、使用者が始業、終業時刻を把握し、労働時間を管理することを同法が当然の前提としていることから、この前提を改めて明確にし、始業、終業時刻の把握に関して、事業主が講ずべき措置を明らかにした上で適切な指導を行うなど、現行法の履行を確保する観点から所要の措置を講ずることが適当である。」との建議がなされたところである。
このため、本基準において、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにすることにより、労働時間の適切な管理の促進を図り、もって労働基準法の遵守に資するものとする。
1 適用の範囲
本基準の対象事業場は、労働基準法のうち労働時間に係る規定が適用される全ての事業場とすること。
また、本基準に基づき使用者(使用者から労働時間を管理する権限の委譲を受けた者を含む。以下同じ。)が労働時間の適正な把握を行うべき対象労働者は、いわゆる管理監督者及びみなし労働時間制が適用される労働者(事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る。)を除くすべての者とすること。
なお、本基準の適用から除外する労働者についても、健康確保を図る必要があることから、使用者において適正な労働時間管理を行う責務があること。
2 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置
(1)始業・終業時刻の確認及び記録
使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を確認し、これを記録すること。
(2)始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。
ア 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
イ タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
(3)自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置
上記(2)の方法によることなく、自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合、使用者は次の措置を講ずること。
ア 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。
イ 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること。
ウ 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。
(4)労働時間の記録に関する書類の保存
労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、3年間保存すること。
(5)労働時間を管理する者の職務
事業場において労務管理を行う部署の責任者は、当該事業場内における労働時間の適正な把握等労働時間管理の適正化に関する事項を管理し、労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図ること。
(6)労働時間短縮推進委員会等の活用
事業場の労働時間管理の状況を踏まえ、必要に応じ労働時間短縮推進委員会等の労使協議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握の上、労働時間管理上の問題点及びその解消策等の検討を行うこと。
●労使が取り組むべき事項
(1) 労働時間適正把握基準の遵守
労働時間適正把握基準は、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき具体的措置等を明らかにしたものであり、使用者は賃金不払残業を起こすことのないようにするために、労働時間適正把握基準を遵守する必要がある。
また、労働組合にあっても、使用者が適正に労働時間を把握するために労働者に対して労働時間適正把握基準の周知を行うことが重要である。
(2) 職場風土の改革
賃金不払残業の責任が使用者にあることは論を待たないが、賃金不払残業の背景には、職場の中に賃金不払残業が存在することはやむを得ないとの労使双方の意識(職場風土)が反映されている場合が多いという点に問題があると考えられることから、こうした土壌をなくしていくため、労使は、例えば、次に掲げるような取組を行うことが望ましい。
・ 経営トップ自らによる決意表明や社内巡視等による実態の把握
・ 労使合意による賃金不払残業撲滅の宣言
・ 企業内又は労働組合内での教育
(3) 適正に労働時間の管理を行うためのシステムの整備
・ 適正に労働時間の管理を行うためのシステムの確立
賃金不払残業が行われることのない職場を創るためには、職場において適正に労働時間を管理するシステムを確立し、定着させる必要がある。
このため、まず、例えば、出退勤時刻や入退室時刻の記録、事業場内のコンピュータシステムへの入力記録等、あるいは賃金不払残業の有無も含めた労働者の勤務状況に係る社内アンケートの実施等により賃金不払残業の実態を把握した上で、関係者が行うべき事項や手順等を具体的に示したマニュアルの作成等により、「労働時間適正把握基準」に従って労働時間を適正に把握するシステムを確立することが重要である。
その際に、特に、始業及び終業時刻の確認及び記録は使用者自らの現認又はタイムカード、ICカード等の客観的な記録によることが原則であって、自己申告制によるのはやむを得ない場合に限られるものであることに留意する必要がある。
・ 労働時間の管理のための制度等の見直しの検討
必要に応じて、現行の労働時間の管理のための制度やその運用、さらには仕事の進め方も含めて見直すことについても検討することが望まれる。特に、賃金不払残業の存在を前提とする業務遂行が行われているような場合には、賃金不払残業の温床となっている業務体制や業務指示の在り方にまで踏み込んだ見直しを行うことも重要である。
その際には、例えば、労使委員会において、労働者及び管理者からヒアリングを行うなどにより、業務指示と所定外労働のための予算額との関係を含めた勤務実態や問題点を具体的に把握することが有効と考えられる。
・ 賃金不払残業の是正という観点を考慮した人事考課の実施
賃金不払残業の是正という観点を考慮した人事考課の実施(賃金不払残業を行った労働者も、これを許した現場責任者も評価しない。)等により、適正な労働時間の管理を意識した人事労務管理を行うとともに、こうした人事労務管理を現場レベルでも徹底することも重要である。
(4) 労働時間を適正に把握するための責任体制の明確化とチェック体制の整備
・労働時間を適正に把握し、賃金不払残業の解消を図るためには、各事業場ごとに労働時間の管理の責任者を明確にしておくことが必要である。特に、賃金不払残業が現に行われ、又は過去に行われていた事業場については、例えば、同じ指揮命令系統にない複数の者を労働時間の管理の責任者とすることにより牽制体制を確立して労働時間のダブルチェックを行うなど厳正に労働時間を把握できるような体制を確立することが望ましい。
また、企業全体として、適正な労働時間の管理を遵守徹底させる責任者を選任することも重要である。
・労働時間の管理とは別に、相談窓口を設置する等により賃金不払残業の実態を積極的に把握する体制を確立することが重要である。その際には、上司や人事労務管理担当者以外の者を相談窓口とする、あるいは企業トップが直接情報を把握できるような投書箱(目安箱)や専用電子メールアドレスを設けることなどが考えられる。
・労働組合においても、相談窓口の設置等を行うとともに、賃金不払残業の実態を把握した場合には、労働組合としての必要な対応を行うことが望まれる。
■1ヶ月残業時間が60時間を超える場合、残業代割増率が25%から50%に増加
 就業規則・賃金規程の見直しは必要ありませんか? 就業規則・賃金規程の見直しは必要ありませんか?
|
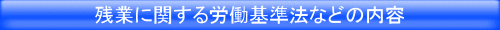
参考にしてください。
■法定労働時間
1週間40時間、1日8時間
■法定労働時間を超えて労働
①法定労働時間を越えて労働させると罰則の適用があります。
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
②法定労働時間を超えて働く約束は無効。無効となった部分は法定労働時間に置き換えられる。
③法定労働時間を超えて働かせるには36協定(=時間外・休日労働に関する協定書)を締結して労働基準監督署に届け出ます。
④法定労働時間を超えて働かせるときは原則割増賃金を支払わなければなりません。
■休日
原則…毎週少なくとも1回の休日を与えます。
例外…4週間を通じて4日以上の休日を与えます
■休憩
1.使用者は、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を労働時間の途中で与えなければなりません。
2.休憩時間は自由に利用させなければなりません。
3.休憩時間は労働者に一斉に付与することが原則ですが、労働者代表との書面による労使協定があるとき(※特定の業種については不要)は、適用が除外されております。
※特定の業種 : 運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署
■割増賃金率
時間外労働25%以上
深夜労働25%以上(原則として午後10時から午前5時)
休日労働35%以上
平成22年4月より1ヶ月60時間を超える残業は割増率50%
■割増賃金の計算式
1時間あたりの賃金額×時間外・休日労働または深夜労働を行わせた時間数×割増率
■時間外労働の上限
a 一般労働者の場合
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1ヶ月 45時間
2ヶ月 81時間
3ヶ月 120時間
1年間 360時間
b 対象期間が3ヵ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者の場合
1週間 14時間
2週間 25時間
4週間 40時間
1ヵ月 42時間
2ヵ月 75時間
3ヵ月 110時間
1年間 320時間
育児又は介護を行う労働者
一定範囲の育児又は介護を行う労働者(男女を問わない)であって、時間外労働を短くすることを使用者に申し出た者に対しては、1ヵ月24時間、1年150時間の限度時間が適用になります
■休業手当
会社側の都合により労働者を休業させた場合、休業させた所定労働日について、平均賃金の6割以上の手当(休業手当)を支払わなければなりません。
■過労死の労災認定…「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」の一部です
●長期間の過重業務について
(ウ) 過重負荷の有無の判断
…疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると、その時間が長いほど、業務の過重性が増すところであり、
……発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、
業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断する…。
●労働時間以外の要因
不規則な勤務…予定された業務スケジュールの変更の頻度・程度、事前の通知状況、予測の度合、業務内容の変更の程度等
拘束時間の長い勤務…拘束時間数、実労働時間数、労働密度(実作業時間と手待時間との割合等)、業務内容、休憩・仮眠時間数、休憩・仮眠施設の状況(広さ、空調、騒音等)等
出張の多い業務…出張中の業務内容、出張(特に時差のある海外出張)の頻度、交通手段、移動時間及び移動時間中の状況、宿泊の有無、宿泊施設の状況、出張中における睡眠を含む休憩・休息の状況、出張による疲労の回復状況等
交替制勤務・深夜勤務…勤務シフトの変更の度合、勤務と次の勤務までの時間、交替制勤務における深夜時間帯の頻度等
作業環境…温度環境、騒音、時差
精神的緊張を伴う業務…【日常的に精神的緊張を伴う業務】業務量、就労期間、経験、適応能力、会社の支援等 【発症に近接した時期における精神的緊張を伴う業務に関連する出来事】 出来事(事故、事件等)の大きさ、損害の程度等
■ 年次有給休暇
●年次有給休暇の日数
雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、10日間の年次有給休暇を付与しなければなりません。その後は勤続年数に応じて下表の日数の年次有給休暇を与えなければなりません。
また、短時間労働者に対しては、所定労働時間又は1週間の所定労働日数により比例付与しなければなりません。
※週所定労働時間30時間以上又は週所定労働日数5日以上の短時間労働者は通常の労働者と同様。
●年次有給休暇の与え方
年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければなりません。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に変更してこれを与えることが出来ます。
また、労働者代表との書面による労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをすることにより、年次有給休暇日数のうち、5日を超える部分に限り年次有給休暇の計画的付与を行うことができます。
●年次有給休暇の買上げと繰越
年次有給休暇を買い上げて労働者に休暇を与えないことは違反となります。
また、使われなかった年次有給休暇は、翌年度に繰り越さなければなりません。時効の期間は2年です。
●不利益取扱いの禁止
年次有給休暇を取得した労働者に対して、その日を欠勤として、精皆勤手当を支給しないとか、賞与を減額するなどの不利益な取扱いをしてはいけません。
● 年次有給休暇中の賃金
年次有給休暇を取得した期間においては就業規則等の定めにより、その日数に応じ、通常の賃金、平均賃金又は健康保険法に定める標準報酬日額相当金額を支払わなければなりません。
■1ヶ月残業時間が60時間を超える場合、残業代割増率が25%から50%に増加
 就業規則・賃金規程の見直しは必要ありませんか? 就業規則・賃金規程の見直しは必要ありませんか?
終身雇用が崩壊し、人情・面倒見のよさだけでは社員はついていきません。
対策をうつなら今がベストです。
|
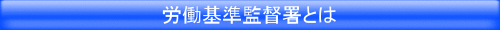
労働基準監督署は、警察署と同じように労働基準法、労働安全衛生法などの労働法規違反を捜査し、地方検察庁に送致するという権限をもっています。
■労働基準監督署が担当する労働基準法の特色は
①個別の労働契約内容を直接規律
労働基準法は、単に使用者に対して規定内容を守ることを強制し、それにより個々の労働者の労働条件を維持、向上させようとするだけでなく、直接個々の労働契約を規律しています。
労働者が、直接、使用者に対して契約内容をこの法律どおりに変更すること求め、労働基準法に定める労働条件を使用者に権利として請求し、実現を図ることができるようにしています。
②違反に対する刑事罰
労働基準法に定める労働条件は、「人たるに値する生活を営むに必要な最低限のもの」(労働基準法第1条)であり、条文は強行規定となっています。
そして違反した場合は、違反内容の軽重に従って「1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金」から「30万円以下の罰金」までの罰則が定められています。
③両罰規定
処罰対象は、行為者処罰主義をとっていますが、両罰規定を設けて事業主にも責任を負わせることとしています。つまり、法違反行為をしたものが、事業主のために行為した代理人、使用人、その他の従業員である場合には、事業主にも本条の罰金刑が課せられます。
④実効確保のための特別な監督行政組織
労働基準法の場合には、全国の都道府県労働局と労働基準監督署に労働基準監督官が配置され、使用者に最低労働条件を守らせるための各事業場への監督、立入り、悪質な違反の送検、取締りが行われます。
■労働基準監督官の権限は
労働基準監督官は、強制的に会社内部に立ち入り、労働基準法などの違反の有無を調査、尋問することができます。
労働基準監督官の2つの権限
①労働基準監督官としての権限
(1)事業場・寄宿舎等の臨検(立入)、帳簿・書類の提出を求める、労使に対する尋問
(2)臨検監督の際には、労働基準監督官証票の携帯
②特別司法警察職としての権限
(1)強制捜査、事情聴取、証拠物の押収等
(2)現行犯以外は捜査令状必要
|
|