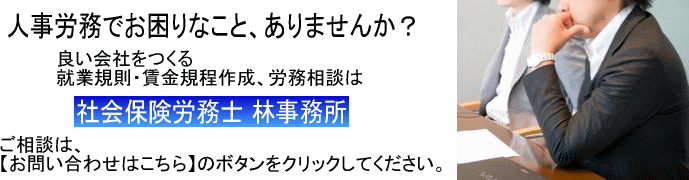| �ИJ�m�̎d������? |
 |
����Љ�ی��J���m�̗тł��B
���x���̈�R�}
�C������20��̂���ł��B
���邭���C�ɑO�����Ɋ撣��܂�! |
|
�y��ȋƖ����e�z
�E�J�����k
�E�A�ƋK��
�E�������x�f�f�A�쐬
�E�e��Z�~�i�[�̊J��
�E�Љ�ی��e�펖�� |
�Љ�ی��J���m�ю������́A�J�����k�A�A�ƋK���A�����ސE�����x�v�A�e��Z�~�i�[�̊J�Âɗ͂����Ă���܂��B
�l���J���̐��ƂƂ��āA��ƌo�c���o�b�N�A�b�v�������܂��B
|
�y���ݒn�z
�Љ�ی��J���m�ю�����
��\�@�с@���m
��274-0071
��t���D���s�K�u��1-13-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
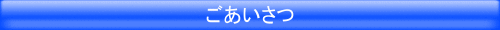
�I�g�ٗp���x�������錻�݁A�J���҂̌����ӎ��������Ȃ炴��Ȃ�����ɓ˓����A�J�g�̃g���u�����}�����Ă��܂��B���̎���̐��Ј��́A�I�g�ٗp���x��M���鎖���ł��Ȃ��킯�ł�����A���ސE�ɂ���邩�킩��Ȃ��Ƃ����s���̒��œ����Ă��܂��B
�]�ƈ�����������邽�߂Ɍ����ӎ��������Ȃ��Ă���͓̂��R�Ƃ����܂��B�h���Ј��E�p�[�g�^�C�}�[�ƂȂ�Ȃ�����ł��B
�ǂ����Ă��A�l���J���̖��͌�ɂȂ肪���ł��B�������A��Ƃ̔��W���肤�̂Ȃ�A�l���J���̖�肪�N����Ȃ��悤�A���R�ɖh�~����藧�Ă��l���Ă������Ƃ��K�v�ł��B
�������x�̕s���A�J���Ǘ��̕s�����������݂��Ă��܂��B���ɕs�����c�ƂȂǂŁA�K�v�ȏ�Ɂy�����J�舫���̃��X�N�z��w�����Ă����Ƃ͐���������܂��B
���̂悤�Ȗ��ʂȃ��X�N��w����Ȃ��悤�A�l���J���̉��P�̂���`�����ł��A��Ƃ̔��W�̂��͂ɂȂ��K���ł��B�@�@
|
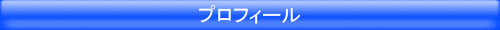
��\��
|
�с@���m |
�N��
|
40�ł����A�C������20��ł��B |
| �o�� |
��w���ƌ�A���Z�@�Ζ����܂����B
��ɉc�ƁE�Z��(�������́E�R���܂�)�E�O���ב�(�A���E�A�o)�̋Ɩ����s���܂����B
���̌�A�Љ�ی��J���m�������Ŏ����o���ςݓƗ����܂����B
|
| �Z�~�i�[���� |
�u���{��������N�����v
�u�Œ�m���Ă��������N���̃|�C���g�v
�u�m���ē����鏕�����̘b�v
�u���Ј��ɑ���Ή���v
�u��Ɛl�Ƃ��Ă̈�ʏ펯�v
�ƊE���u�����������v�ɂ��L�����f�ڂ���܂����B |
| � |
�e�j�X�E�o�C�N�E�o�[�x�L���[�ł��B
�e�j�X�͂��܂��鎞�Ԃ��Ȃ��̂ł����A
���ɂ͏o�Ă��܂��B
���s���[���̂����v���[�ɏd�_��u���Ă��܂��B |
���i
|
�����ŁA�b���₷�����i�ł��B |
| �w�� |
���݁A�^�ʐM����w�Ŋw��ł��܂��B2�ڂ̑�w�ɂȂ�܂��B
���ɂȂ��Ċw��̊y�������킩���Ă��܂����B |
|

���ݒn
|
��t���D���s�K�u��1-13-3 |
| �d�b |
047-469-2039 |
D-FAX
|
020-4666-4078
|
| E-mail |
info��88455.net
�������ɕϊ����Ă��������B |
| ��\ |
�с@���m |
���i |
����Љ�ی��J���m
�o�^�ԍ��@12020061
��t���Љ�ی��J���m��� |
|
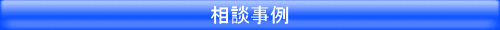
�����������k����P��������
����ƋK�́c���Ј��E�p�[�g�܂ߖ�V�O�O��
�z�[���y�[�W�����Ă��������A�y�Ζ��V�t�g�����P�������z�Ƃ̑��k�˗�������
�܂����B
�c�Ɓ{�x���o�̍��v���Ԃ�200���Ԓ����������P�[�X�B
�S�Ј��̎c�ƁE�x���o�̖����������̎��Z�͖�1���~�Əo�܂����B
���ɂP���x��ł��Ȃ����Ј��������B���Ȃ荓���ł����B
���A�h�o�C�X��������
�@�@�ߏ���(�R���v���C�A���X)�̈ӎ����Ⴗ�����̂ŁA�����E���ے��Ɉӎ�����
�悤�����������������܂����B
�����ԘJ�����Е��ɂȂ��Ă������߁A�C������悤�˗��B
�u�x�ނ��ƁA�c�Ƃ��Ȃ��ŋA�邱�Ƃ͈������Ƃł͂Ȃ��v�Ƃ����ӎ��t�����s��
�A�܂��ߘJ���̊댯�����ٔ���ƉߘJ���F���ł����������B
�����̐ӔC�͏d�����̂ɂȂ邱�Ƃ�m�点�܂����B
�A���Ј��̃V�t�g�̌������B�o�Ύ��Ԃ������W���Ԃɂ��A8���Ԃ���ꍇ�̓p
�[�g�^�C�}�[�Ɏd�������Ă��炤�`���Ƃ�B����͌���̐ӔC�҂Ƃ��b��������
�{�B
���Ј��̎c�Ǝ��ԒP�����p�[�g�^�C�}�[�̎����̂ق����������߁A���Ј��̌�
�N�Ǘ��A�l����̖ʂ������ƂɂƂ��ėL���ɂȂ�܂��B
�B�c�Ƃ̑������Ј��Ɏw���B���ɃV�t�g�̍H�v���Ăъ|���܂����B
�܂��A���Ј����x��ł���Ƃ��ɁA�{�Ђ���x�X�ɕ����l���̐����B
�Ƃɂ����x���𑝂₵�A�Ȃ�ׂ��c�Ƃ������Ȃ������ɂ����Ă����Ƃ������Ƃ�
�͂𒍂��܂����B
���������Ă���2�N���o���A���Ȃ�̉��P���݂�ꌋ�ʓI�ɐl����̗}���A���Ј�
�̔�J�~�ς̌����ɂ��Ɩ��~�X�̍팸�E�����Ǝd���̏[���A�@�ߏ���ɂȂ�
���Ă��܂��B
�������A������Ж����E���Ј��̕��X���ϋɓI�ɉ��P�������Ƃ��傫�Ȑ��ʂ�
���т����̂ł��B���������珕�������Ƃ���ŕ���������Ă��܂�����܂�
�B
��Ж����E���Ј�����̂ƂȂ��ēw�͂������Ƃ��������ꂽ����ł��B
�����������k����Q��������
����ƋK�́c���Ј��E�p�[�g�܂ߖ�S�O��
�z�[���y�[�W�����Ă��������A�y�������x�̌��������s�������z�Ƃ̑��k�˗���
����܂����B
���k�̗��R�́A���܂ł͉Ɠ��H�ƓI�ȉ�Ђł������A�g��H������ݏ]�ƈ�����
���Ă������߁A�Г������Ɏ��g�݂����Ƃ̂��Ƃł����B
���^�̌`�͎В��݂̂������Ō��߂Ă��āA��{���ƋZ�p�蓖�����ł����B
���_�́A�c�Ƒ���u��{���v�Ƃ������ڂ̒��Ɋ܂߂Ă��܂��Ă������Ƃł��B
�u��{���v�̒��̂����炪�c�Ƒ�Ȃ̂��A���^���ׂ��݂������ł͕�����Ȃ���
�Ԃł����B
�c�Ƒ�Ńg���u�����N�����ꍇ�A�c�Ƒオ������Ȃ̂����킯�����Ȃ���Ԃ�
�����̂ŁA
��ЂɂƂ��Ă��Ȃ�s���ɂȂ邱�Ƃ��\�z����܂����B
�܂��A�T�S�O���ԘJ��������Ă��Ȃ���Ԃł����̂ŁA�Ɩ��̒��g���������A
���Z�𐄐i���邱�ƂɂȂ�܂����B
���A�h�o�C�X��������
�@��{���Ǝc�Ƒ�̍��ڂ��邱�ƁB
�]�ƈ����ꂼ��̎c�Ǝ��Ԃ������Ԃ��Ă���̂��o���Ă��炢�܂����B
�A���݂̋��^�������Ȃ��悤�A��Ђ̎��Ԃɂ�������{�����Đݒ肵�A�A�ƋK
�����쐬���܂����B
�]�ƈ��ɂ悭�������A���ӂ��Ă��炢�܂����B
�B���ʂȎc�Ƃ͉�ЂɂƂ��Ă��l����ɂȂ���A�Ј��ɂƂ��Ă��s���̒~��
�E���`�x�[�V�����̒ቺ�ɂȂ�A
�ǂ���ɂƂ��Ă��ǂ����Ƃ��Ȃ����Ƃ𗝉����Ă��炢�܂����B
���������Ă�����s�܂łɔ��N������܂������A���ł͎Г�����������Ė��ʂ�
�l�������A�Ј��Ƃ��Ă������₷�����ɂȂ��Ă��܂����B
�������A������Ж����̕��X���ϋɓI�ɉ��P�������Ƃ��傫�Ȑ��ʂɌ��т�
���̂ł��B���������珕�������Ƃ���ŕ���������Ă��܂�����܂ŁB
��Ж����̓w�͂̂��܂��̂ł��B
�����������k����R��������
����ƋK�́c���Ј��E�p�[�g�܂ߖ�U�O��
�z�[���y�[�W�����Ă��������A�y�A�ƋK���E�l�����x�̓����z���������Ƃ̑��k
�˗�������܂����B
���A�h�o�C�X��������
�@��E���Ƃɐg�ɂ��Ă��炢�����d�����ׂ����s�b�N�A�b�v���Ă��炢�܂���
�B����ɂ��A�]�ƈ��̂��ׂ��ڕW����̓I�ɂȂ�܂����B
�A�����̐v���s���܂����B
��Ђ̎���ɂ�������{����ݒ�
��E���Ƃɖ�E�蓖��ݒ肵�܂����B
�B�l���l�ە\���쐬���A���i�E�ܗ^����Ɋ��p�ł���悤�ɂ��܂����B
���P�N������܂������A���̊�Ƃɂ������A�ƋK���Ɛl�����x���Ă��܂���
�B�l�����x�̓����́A���̊�Ƃ��ƊE���������悤�ł��B
��E���Ƃ̋Ɩ����e���͂����肵�A�g�ɂ���ׂ����̂��ڂɌ�����悤�ɂȂ�
�����߁A�]�ƈ��͖ڕW���ӎ����ē����悤�ɂȂ����Ƃ̂��Ƃł��B
�����������k����S��������
����ƋK�́c���Ј��E�p�[�g�܂ߖ�Q�O��
�y�������z���������Ƃ̑��k������܂����B�ŗ��m�̏Љ�ł����B
���A�h�o�C�X��������
�@���^��������x�����Ă���̂������Ă��炢�܂����B
���^�����ԑ��ꂩ�炵�Ă����Ȃ�����������߁A
�����������Ă��]�ƈ��̃��`�x�[�V�����A�b�v�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ɛ����B
���ɖڕW��B�����Ă��������������āA������������Ӗ�������܂���ł�
���B
�]�ƈ��Ƀv���b�V���[�������邽�߂Ȃ�A�������͓������Ȃ��ق��������Ɖ�
���܂����B
�A������ܗ^�ɔ��f����ق����A�o�c�҂ɂƂ��Ă��葱�����ȒP�ł��₷����
�������܂����B
�������������������邱�Ƃɂ��A�ܗ^����ɂ��邱�ƂɂȂ�܂����B
�����ɕ�����������ƁA�Г����M�N�V���N���ăg���u���̂��ƂɂȂ邱�Ƃ�����܂��B
�ڕW�B���̂��߁A�u���q�l�ɉ������肷��v�Ƃ����s�ׂ��o�Ă��邱�Ƃ�����A
��Ƃ̐M�p�������邱�Ƃ�����܂��B
�����������k����T��������
����ƋK�́c���Ј��E�p�[�g�܂ߖ�T�O��
���^�K���������������Ƃ̑��k������܂����B
���A�h�o�C�X�������ƁB
�@�l�X�Ȏ蓖������܂������A���ɂ͈Ӗ��s���Ȏ蓖������܂����B
�ǂ̎蓖���K�v�ŁA�ǂ̎蓖���`�����̂��̂������邱�Ƃɂ��܂����B
�A�K�v�Ȏ蓖�݂̂��c���A���݂̋��^��������Ȃ��悤�v���܂����B
�B�A�ƋK�����쐬���Ă���P�O�N�ȏ�o���Ă����̂ŁA�A�ƋK���S�ʂ̌�������
�����߂��܂����B
���c�Ǝ蓖�̌v�Z�ɂ́A�����Ƃ��āA�y��{���{�e��蓖�̍��v�z���玞�����Z
�o���Čv�Z���܂��B
�c�Ǝ蓖�́u��{�����������ƂɌv�Z��������v�Ɗ��Ⴂ���Ă���o�c�҂͂�
�Ȃ肢�܂��̂ŁA���ӂ��K�v�ł��B
�����������̑��A�J�������ύX�E�����E��N�E�ސE�E���ٖ��E�玙���x�Ɗ֘A�ȂǑ������k������܂��B��������
|
���Љ�ی��J���m�Ƃ�?��
�Љ�ی��J���m�Ƃ�
���Ƃ̔��W�ƘJ���҂̕�������Ƃ����g����S�����Љ�ی��J���m�@�Ɋ�Â����I���i�҂ł��B
�Љ�ی��J���m���x�́A��Ƃ̎��v�ɉ����A�J���Љ�ی��W�̖@�߂ɐ��ʂ��A�K�ȘJ���Ǘ����̑��J���Љ�ی��Ɋւ���w�����s��������Ƃ̐��x�ł��B
���̐��x�́A�J���E�Љ�ی��Ɋւ���@�߂̉~���Ȏ��{��}��A���Ƃ̌��S�Ȕ��B�ƘJ���҂����̕����̌����ړI�Ƃ����Љ�ی��J���m�@�i���a43�N6��3���@����89���j�ɂ���߂��Ă��܂��B
�Љ�ی��J���m�Ƃ́A�Љ�ی��J���m�@�Ɋ�Â��A���N���A�����J����b�����{����Љ�ی��J���m�����ɍ��i���A���A2�N�ȏ�̎����o���̂���҂ŁA�S���Љ�ی��J���m��A����ɔ�����Љ�ی��J���m����ɓo�^���ꂽ�҂������܂��B
�Љ�ی��J���m�̎�ȋƖ�(�|�C���g)
1.�l���J���R���T���e�B���O(���k�Ɩ�)
�@�@�������x�E�ސE���v�E�J�����ԁE�l�����x�ȂNJ�ƂƏ]�ƈ������Ԑ��x�̐�
�@�@�v
�@�A�̗p�E��N�E�����ȂǏ]�ƈ��Ƃ̊ԂɋN����l�X�Ȗ��ɑ��������̒��
2.�A�ƋK���E�����E�ސE���K���E�l���ی�K���Ȃǂ̍쐬
3.�������̒�āE�葱
4.��Ƃ̘J���Ɋւ���㗝��s
�@�J����@�A�J�Еی��@�A�ٗp�ی��@�A���N�ی��@�A�����N���ی��@�A�����N���@���Ɋ�Â��\����͏o
�A�x�ƕ⏞�A�o�Y�玙�ꎞ���A�o�Y�蓖���A���a�蓖���Ȃǂ̐���
�B�L���Љ�Ƌ��\���A�h�����Ɠo�^�E�͏o�\���A���ی����ƎҎw��\�����̎葱��
�C�J���ی�(�J�Еی��E�ٗp�ی�)�A�Љ�ی��̉����E�E��
��L�A��ȋƖ�(1.4)�̋�̓I���e�͉��L�̂Ƃ���ł��B
1.�l���J���R���T���e�B���O(���k�Ɩ�)
�k�ٗp�Ǘ��l
�@���l�ނ̕�W�E�̗p
�@���l�ނ̓K���z�u�Ɛl���ٓ��i�z�]�E�o���Ȃǁj
�@�������K���ƒ���
�@���ސE�Ɖ���
�@���h���Ј��E�_��Ј��E�p�[�g�E�O���l�E����҂Ȃǂ̌ٗp�Ǘ�
�k�A�ƊǗ��l
�@���J�����ԁi�J�����Ԃ͈̔́A�ό`�J�����Ԑ��A�݂Ȃ��J�����Ԑ��Ȃǁj
�@���L���x��
�@���玙�x�ɁE���x��
�@���j���ٗp�@��ϓ��Ȃǂ̏]�ƈ��̏A�ƂɊւ��鎖��
�k�l���Ǘ��l
�@���E�\���i�i�����j���x�╡���^�l�����x
�@���l���]�����x�i�A�Z�X�����g�j
�@���ڕW�Ǘ��E�ʒk���x
�@�������ސE�җD�����x
�@�����Ȑ\�����x
�@���Г����吧
�@�����s�������x
�@�������[���A�b�v�E���`�x�[�V�����Ǘ��Ȃ�
�k�����Ǘ��l
�@���E�\����E����
�@���N��Ȃǂ̒������x����ёސE�����x�̐v
�@�����蓖�Ɗ��������̐v�Ǝ���
�@�����ʎ�`�ܗ^���x��X�g�b�N�E�I�v�V�����Ȃǂ̃C���Z���e�B�u���x�̐v�Ȃ�
�k���������l
�@���@�蕟���i�Љ�ی��Ȃǁj�Ɩ@��O����
�@�����������{�݂ƕ����������x�i���������܂ށj
�@����ƕ���
�@���J�t�F�e���A�E�v�����̐v�Ȃ�
�k����P���l
�@������P���v��̍���
�@���Ǘ��Ҍ��C�Ȃǂ̊K�w�ʋ���P���̊��Ǝ��{
�@��OJT�}�j���A���̍쐬
�@�����Ȍ[���x�����x�̐v�Ȃ�
�k���̑��J���Ǘ��l
�@�ʘJ�������̎��O�h�~�E�����A���������ψ���ɂ����邠������㗝��J���f�f���s���܂��B
�J�����Ԃ̉��P���A�ΘJ�ӗ~��傢�ɍ��߂܂��B�Љ�ی��J���m�́A�l���ȂǘJ���Ǘ��S�ʂɂ��ẴX�y�V�����X�g�Ƃ��āA���Ə��̌��S�Ȕ��W�ɍv�����܂��B
�E��������㗝
�E�J�������̉��P�w��
�E�A�ƋK���̌�����
4.��Ƃ̘J���Ɋւ���㗝��s
���ގЂȂǂ̎葱
�J���Љ�ی��̔N�x�X�V�����i5���j�A�Љ�ی��̎Z��Ɩ��i7���j�́A�����I�ɂ��傫�ȕ��S�ƂȂ��Ă��܂��B
�@�Љ�ی��J���m�́A�J���Љ�ی��̎����葱�����X�s�[�f�B�ɁA�������I�m�ɏ����������܂��B
�m�Ɩ��̓��e�n
�E�J���Љ�ی��̉����E�E��
�E�e�틋�t���̐���
�E���[���ނ̍쐬
�E���܂��܂Ȏ葱��
|
���l���ی���j��
�Љ�ی��J���m�̎��`��
�i�Љ�ی��J���m�@��Q�P���@���`���@�E�@���@��Q�V���̂Q�@�g�p�l�̎��`���j
�������Љ�ی��J���m�͂��ׂĖ@���ɂ���Ď��`�����ۂ���Ă���܂��B
���^�v�Z�ϑ��Ȃǂ̊�Ə��A�l���ւ̍אS�̒��Ӌ`�����܂��B���S���Ă����k�������B
�l���ی���j
�ю�����
����Љ�ی��J���m�@�с@���m
�@�����́A�l���E�J���Ɋւ���@�I�m���E�T�[�r�X�̒�ʂ��Ċ�Ƃ̔��W�ɍv�����邱�Ƃ���{���O�Ƃ��A���q�l�ɍő������������T�[�r�X����邱�Ƃ��g���Ƃ��Ă���܂��B
�@�����ł́A�l���ی�Ɋւ�����j�����L�̒ʂ��߁A�Ј��S���Ōl���ی�ɓw�߂Ă܂���܂��B
�E�����́A�l���ی�@���̑��̊֘A�@�K�����炵�A�ۗL����l���̈��S�Ǘ��̂��ߕK�v���K�ȑ[�u���u���܂��B
�@�����ł́A���̎�舵���l���̘R�k�A�Ŏ��܂��͚ʑ��̖h�~���̑��̌l���̈��S�̂��߁A�g�D�I�A�l�I�A�����I����ыZ�p�I�Ȉ��S�Ǘ��[�u���u���܂��B
�E�����́A�U�肻�̑��s���̎�i�ɂ��l�����擾�����A�܂��A��舵���l���̗��p�ړI�̓���E�����ɓw�߂܂��B
�@�����ł́A�l�����擾����ꍇ�A�܂��͗��p�ړI��ύX����ꍇ�́A���̗��p�ړI�����\���邱�ƂƂ��A�{�l���璼�ړ��Y�{�l�̌l�������ʓ�����擾����ꍇ�͗\�ߖ{�l�ɑ��āA���̗��p�ړI�����܂��B�A���擾�̏���݂ė��p�ړI�����炩�ł���ƔF�߂���Ƃ����A�����ȗ��R������ƔF�߂瓾��Ƃ��͂��̌���ł͂���܂���B
�E�����́A�����Ƃ��āA���肳�ꂽ���p�ړI�͈͓̔��Ōl������舵���܂��B
�@�����ł́A�@�߂��̑������ȗ��R������ꍇ�Ŗ{�l�̓��ӂ邱�Ƃ�����ł���Ƃ��������A�\�ߖ{�l�̓��ӂȂ��ŁA���肳�ꂽ���p�ړI�̒B���ɕK�v�Ȕ͈͂��āA�l������舵�����Ƃ͒v���܂���B
�E�����́A�l�f�[�^�𐳊m���ŐV�̓��e�ɕۂ��A�K�v���Ȃ��Ȃ�Ίm���ɔp������悤�w�߂܂��B
�@
�E�����́A�����ȗ��R������ꍇ�������A�{�l�̓��ӂȂ��l�f�[�^���O�҂ɒ��܂���B �@�����ł́A�擾�����l�f�[�^�̑�O�Ғ͌����Ƃ��Ă���܂���B��O�I�Ɍl�f�[�^�����̂́A�@�߂Ɋ�Â��ꍇ�A�܂��͐l�̐����A�g�̂܂��͍��Y�̕ی�Ȃǂ̂��ߓ��ɕK�v������ꍇ�ł����āA�{�l�̓��ӂ邱�Ƃ�����ȏꍇ�Ɍ��肳��܂��B
�E�����́A�Ј��ɑ��l���ی�̂��߂ɓK�ȊēE������s���܂��B
�E�����́A�{�l����ۗ̕L�l�f�[�^�̊J���A�����A���p��~���̐����ɑ��ēK�ɑΏ����܂��B
�@�����ł́A���ږ{�l����擾�����l�f�[�^�i�ۗL�l�f�[�^�j�Ɋւ��āA�{�l����J�������߂�ꂽ�Ƃ��́A�����̋Ɩ��̎��{�ɒ������x����y�ڂ������ꂪ����ꍇ���̑��s���ȗ��R������ꍇ�������A�{�l�ɑ��A���Y�ۗL�l�f�[�^���J�����܂��B�@���̍ۂ̎葱���Ɋւ��Ă͕ʓr��߂���̂Ƃ��܂��B�܂��A�{�l����̐����ɂ��A���p�ړI�̒B���ɕK�v�Ȕ͈͓��ɂ����āA�ۗL�l�f�[�^�̓��e�̒����A�lj��܂��͍폜���s���܂��B
�@�Ɩ��ϑ��悩��ϑ������l�f�[�^�Ɋւ��ẮA�ϑ�����ē��闧��ɂ���܂��B���������܂��Ă����͕ۗL�l�f�[�^�ɊY�����Ȃ����߁A�Ɩ��ϑ��悩���������l�f�[�^�Ɋւ��ẮA�]�ƈ��{�l�l����̌l���J���A�����A�lj��A�폜�̈˗��ɂ͒��ډ����邱�Ƃ͂������܂���B
|
|